下村健寿「『復活の日』から読み解くバイオロジー」について ― 2022-02-06 09:58

相変わらず新型コロナウイルスが猛威をふるっている。オミクロン株は弱毒化したとはいえ、亡くなる方はいるので対策を緩めるわけにもいかず、本当に舵取りは難しい。いい加減落ち着いてほしいものだが、沈静化にはまだまだかかるかもしれない。
さて、ウイルスを扱った書物は数々あるが、分子生物学の視点から生命の本質に迫り、もはや古典的名著と言える福岡伸一『生物と無生物のあいだ』(講談社現代新書、2007年)も始めはウイルスの話から始まる。第1章で、福岡は、自身も学んでいたロックフェラー大学(元ロックフェラー医学研究所)に在籍していた野口英世について述べる。梅毒、ポリオ、狂犬病、黄熱病の病原体を発見したと発表し、西アフリカで黄熱病に倒れた野口の功績をある程度認めながらも、「野口の主張のほとんどは、今では間違ったものとしてまったく顧みられていない」と手厳しく批判している。野口が間違ってしまった理由は、梅毒以外の病原体はすべてウイルスであり、当時の顕微鏡の解像度ではウイルスが小さすぎて捉えられなかったからだ。1章で福岡は、「野口の研究は単なる錯誤だったのか、あるいは故意に研究データを捏造したものなのか、はたまた自己欺瞞によって何が本当なのか見極められなくなった果てのものなのか」と書いているが、この部分についての反論を最近読んで、面白いと思ったので、ここに記しておく。
小松左京は、2001年から〈小松左京マガジン〉という同人誌を作り、年に4冊の季刊ペースで発行していた(小松の死後も刊行され、2013年50巻で終刊)。小松に縁のある作家、研究者らが好きなテーマで随想や論文、小説を発表していたものである。その寄稿者の一人に下村健寿という方がおり(医学者、医師、元オックスフォード大学研究員、現福島県立医科大学教授)、海外での小松左京原作映画の受容のされ方、「さよならジュピター」を再評価する論考などを執筆されていた。26巻に掲載された「1984『スター・ウォーズ』に潰された映画」が「さよならジュピター」とリンチ版「デューン砂の惑星」を取り上げていて滅法面白かったので、他のも読んでみようと思ったのだ。
あにはからんや、31巻から7回連載された「『復活の日』から読み解くバイオロジー」は、専門を生かしてウイルスの発見や黒死病、火星生命の可能性、細菌兵器や抗生物質について、科学的知見に基づいた論考がなされており、非常に読み応えがあり、知的好奇心を刺激される、優れた評論になっていた。
その第1回に、福岡の野口批判に対する反論が載っている(本の題名は載っていないが、内容からして明らかだろう)。その骨子は、野口の研究が「間違っていた」のは確かだが、それは決して「捏造」とは言えず、可能性であるにせよ、「捏造」という言葉を使うのは科学者に対して失礼であろうというものだ。最初はどっちでもいいのではと思って読んでいたが、科学というのは間違いと訂正を繰り返して発展していくものであり、「間違い」と「捏造」は天と地ほども違うという下村の主張には大変説得力があり、なるほどと思わされた。他の回も一気に読んだが、いずれも根拠をはっきりと示したうえでの論考で、一読の価値がある。
下村氏は、昨年『オックスフォード式最高のやせ方』(アスコム、2021年)という本を上梓されておられるが、健康本だけでなく、ぜひともこれらの生物学に関する原稿をまとめて出版してほしいものである(売れ方は健康本にかなわないかもしれないが)。
さて、ウイルスを扱った書物は数々あるが、分子生物学の視点から生命の本質に迫り、もはや古典的名著と言える福岡伸一『生物と無生物のあいだ』(講談社現代新書、2007年)も始めはウイルスの話から始まる。第1章で、福岡は、自身も学んでいたロックフェラー大学(元ロックフェラー医学研究所)に在籍していた野口英世について述べる。梅毒、ポリオ、狂犬病、黄熱病の病原体を発見したと発表し、西アフリカで黄熱病に倒れた野口の功績をある程度認めながらも、「野口の主張のほとんどは、今では間違ったものとしてまったく顧みられていない」と手厳しく批判している。野口が間違ってしまった理由は、梅毒以外の病原体はすべてウイルスであり、当時の顕微鏡の解像度ではウイルスが小さすぎて捉えられなかったからだ。1章で福岡は、「野口の研究は単なる錯誤だったのか、あるいは故意に研究データを捏造したものなのか、はたまた自己欺瞞によって何が本当なのか見極められなくなった果てのものなのか」と書いているが、この部分についての反論を最近読んで、面白いと思ったので、ここに記しておく。
小松左京は、2001年から〈小松左京マガジン〉という同人誌を作り、年に4冊の季刊ペースで発行していた(小松の死後も刊行され、2013年50巻で終刊)。小松に縁のある作家、研究者らが好きなテーマで随想や論文、小説を発表していたものである。その寄稿者の一人に下村健寿という方がおり(医学者、医師、元オックスフォード大学研究員、現福島県立医科大学教授)、海外での小松左京原作映画の受容のされ方、「さよならジュピター」を再評価する論考などを執筆されていた。26巻に掲載された「1984『スター・ウォーズ』に潰された映画」が「さよならジュピター」とリンチ版「デューン砂の惑星」を取り上げていて滅法面白かったので、他のも読んでみようと思ったのだ。
あにはからんや、31巻から7回連載された「『復活の日』から読み解くバイオロジー」は、専門を生かしてウイルスの発見や黒死病、火星生命の可能性、細菌兵器や抗生物質について、科学的知見に基づいた論考がなされており、非常に読み応えがあり、知的好奇心を刺激される、優れた評論になっていた。
その第1回に、福岡の野口批判に対する反論が載っている(本の題名は載っていないが、内容からして明らかだろう)。その骨子は、野口の研究が「間違っていた」のは確かだが、それは決して「捏造」とは言えず、可能性であるにせよ、「捏造」という言葉を使うのは科学者に対して失礼であろうというものだ。最初はどっちでもいいのではと思って読んでいたが、科学というのは間違いと訂正を繰り返して発展していくものであり、「間違い」と「捏造」は天と地ほども違うという下村の主張には大変説得力があり、なるほどと思わされた。他の回も一気に読んだが、いずれも根拠をはっきりと示したうえでの論考で、一読の価値がある。
下村氏は、昨年『オックスフォード式最高のやせ方』(アスコム、2021年)という本を上梓されておられるが、健康本だけでなく、ぜひともこれらの生物学に関する原稿をまとめて出版してほしいものである(売れ方は健康本にかなわないかもしれないが)。
小松左京その3(女シリーズ・芸道もの) ― 2012-03-05 00:00
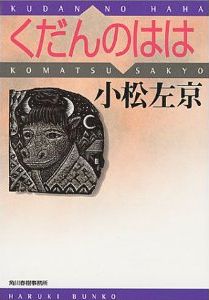
本年も昨年に引き続き、小松左京の旧作を読んでいく。実は女シリーズ・芸道ものは若い頃はほとんど読んでおらず、今回初めて読んでみた。結論から言えば、女シリーズは出来不出来の差が大きい。「ハイネックの女」「昔の女」などホラー系統の作品は残念ながらフォーミュラ・フィクションを脱しきれていない。「写真の女」のオチはあんまりだと思うし、「歌う女」はもう少しひねれば傑作になったかもと惜しまれる作品だ。芸道ものには、それほどハズレはない。ハルキ文庫版で『くだんのはは』と『高砂幻戯』の二冊を読めば、女シリーズは10編全てを、芸道ものは全12編のうち10編を読むことができる。全て読んでみて、傑作と思ったのは以下の三篇である。
「旅する女」(『高砂幻戯』所収)
四年前に失くしたあるものを探すために世界中を一人で旅する女、滝川夫人とタヒチのホテルで出会った「彼」は、二十年前の学生時代に付き合っていた水商売の女性を思い出す。滝川夫人は、ずっと彼が行方を探している彼女に似ていたのだ。どこが似ているのかと問う夫人に対して「彼」は答える。「私のとよく似ていながら、まったくちがった世界、すれちがうことはできても絶対に出あえないような世界を、一人で旅していらっしゃる所……」。求めても得られない何かを探しているという点で、夫人と「彼」は同一なのである。得られないとわかっていてもなお失われたものを求めざるを得ない人間の業の深さ、凄まじさ。これを本編の結末は見事にえぐり出し、読者に強烈な印象を残す幕切れとなっている。
「流れる女」(『くだんのはは』所収)
おそらく金沢がモデルと思われる古都K市を舞台に、還暦間近の主人公の恋と義父の恋、息子の恋、三世代にまたがる恋が同時に描かれる。三年前に妻を亡くした「私」は、どう見ても三十代にしか見えない五十すぎの女性、芸事の師匠をしている小出ゆきと知り合い、恋に落ちる。同じく妻を亡くした八十近くの義父と暮らす「私」は、どうやらゆきと義父が会っていることに気づく。そんなとき、息子の一郎が芸者と結婚したいと連絡をしてきた。「私」が実際に会うことになった息子の結婚相手とは……。詳細な情景描写から始まって、お茶道具、小唄端唄など芸事の具体的な叙述に至るまで、本編は見事なリアリズムに貫かれている。このリアリズムがあってこそ、あっと驚く非現実的な結末の衝撃が保証されているわけだ。女シリーズの白眉というべき傑作である。
「天神山縁糸苧環(てんじんやまえにしのおだまき)」(『高砂幻戯』所収)
上方落語の大物桂文都師匠(モデルは桂米朝)の弟子小文が真打ちに昇進することになり、その襲名披露興行で、師匠は封印していた大ネタ「立ち切れ」をやることになる。「立ち切れ」の中に出てくる芸者小糸と、若かりし文都を恋して非業の死を遂げた芸者小糸との人生とが絡み合い、もつれ合って、物語は文都演じる「立ち切れ」のクライマックスへと至る……。これ、ホントにいい話で、自分は結末付近でじわりと感動が湧き上がり、涙をこらえることができなかった。小松左京の作品で泣いたのは初めてかもしれない。山崎正和は文春文庫版『日本沈没』の解説で「この作者の本質は抒情詩人である」と鋭い指摘をしているが、本編などを読むとまさにその通りに思えてくる。
以上三篇、未読の方はぜひとも読んでみてほしい。小説的完成度を放棄したと思われがちな小松左京ではあるが、その気になれば十分完成された小説を書くことができたのだということがわかってもらえると思う。ただし、考慮すべき点は、「流れる女」はピランデルロのある戯曲を元にしており、「天神山縁糸苧環」は落語「立ち切れ」の変奏曲に他ならないという事実である。「鷺娘」という芸道ものの中で、ノルウェー人のハンスに「日本固有のものって何だ?」と尋ねられた作家大杉(無論モデルは小松自身)が「日本オリジナルなものより、世界中から流れこんだいろんなエレメントの、後世へかけての受け入れ方、発展のさせ方、変形のしかたに、日本固有のものがあるかもしれない」と語っているが、まさにそのオリジナルに対する「発展のさせ方、変形のしかた」の巧さに、小松左京の魅力の一つはあるのではないだろうか。
「旅する女」(『高砂幻戯』所収)
四年前に失くしたあるものを探すために世界中を一人で旅する女、滝川夫人とタヒチのホテルで出会った「彼」は、二十年前の学生時代に付き合っていた水商売の女性を思い出す。滝川夫人は、ずっと彼が行方を探している彼女に似ていたのだ。どこが似ているのかと問う夫人に対して「彼」は答える。「私のとよく似ていながら、まったくちがった世界、すれちがうことはできても絶対に出あえないような世界を、一人で旅していらっしゃる所……」。求めても得られない何かを探しているという点で、夫人と「彼」は同一なのである。得られないとわかっていてもなお失われたものを求めざるを得ない人間の業の深さ、凄まじさ。これを本編の結末は見事にえぐり出し、読者に強烈な印象を残す幕切れとなっている。
「流れる女」(『くだんのはは』所収)
おそらく金沢がモデルと思われる古都K市を舞台に、還暦間近の主人公の恋と義父の恋、息子の恋、三世代にまたがる恋が同時に描かれる。三年前に妻を亡くした「私」は、どう見ても三十代にしか見えない五十すぎの女性、芸事の師匠をしている小出ゆきと知り合い、恋に落ちる。同じく妻を亡くした八十近くの義父と暮らす「私」は、どうやらゆきと義父が会っていることに気づく。そんなとき、息子の一郎が芸者と結婚したいと連絡をしてきた。「私」が実際に会うことになった息子の結婚相手とは……。詳細な情景描写から始まって、お茶道具、小唄端唄など芸事の具体的な叙述に至るまで、本編は見事なリアリズムに貫かれている。このリアリズムがあってこそ、あっと驚く非現実的な結末の衝撃が保証されているわけだ。女シリーズの白眉というべき傑作である。
「天神山縁糸苧環(てんじんやまえにしのおだまき)」(『高砂幻戯』所収)
上方落語の大物桂文都師匠(モデルは桂米朝)の弟子小文が真打ちに昇進することになり、その襲名披露興行で、師匠は封印していた大ネタ「立ち切れ」をやることになる。「立ち切れ」の中に出てくる芸者小糸と、若かりし文都を恋して非業の死を遂げた芸者小糸との人生とが絡み合い、もつれ合って、物語は文都演じる「立ち切れ」のクライマックスへと至る……。これ、ホントにいい話で、自分は結末付近でじわりと感動が湧き上がり、涙をこらえることができなかった。小松左京の作品で泣いたのは初めてかもしれない。山崎正和は文春文庫版『日本沈没』の解説で「この作者の本質は抒情詩人である」と鋭い指摘をしているが、本編などを読むとまさにその通りに思えてくる。
以上三篇、未読の方はぜひとも読んでみてほしい。小説的完成度を放棄したと思われがちな小松左京ではあるが、その気になれば十分完成された小説を書くことができたのだということがわかってもらえると思う。ただし、考慮すべき点は、「流れる女」はピランデルロのある戯曲を元にしており、「天神山縁糸苧環」は落語「立ち切れ」の変奏曲に他ならないという事実である。「鷺娘」という芸道ものの中で、ノルウェー人のハンスに「日本固有のものって何だ?」と尋ねられた作家大杉(無論モデルは小松自身)が「日本オリジナルなものより、世界中から流れこんだいろんなエレメントの、後世へかけての受け入れ方、発展のさせ方、変形のしかたに、日本固有のものがあるかもしれない」と語っているが、まさにそのオリジナルに対する「発展のさせ方、変形のしかた」の巧さに、小松左京の魅力の一つはあるのではないだろうか。
小松左京その2(「すぺるむ・さぴえんすの冒険」) ― 2011-12-31 18:28

前回に続き小松左京の作品を取り上げる。7月以降さまざまなメディアで氏の作品について触れられていたが、なぜか人気の高い『エスパイ』(8月に行われたアンビ夏の例会における小松左京人気作品投票でも堂々一位を獲得)はおいといて、今回取り上げたいのは、『ゴルディアスの結び目』に入っている短編「すぺるむ・さぴえんすの冒険」と「あなろぐ・らヴ(ホントは「う」に濁音)」だ。おそらく大学時代に読んでいるはずだが、再読するまですっかり忘れていた。
「すぺるむ・さぴえんすの冒険」は地球の最高指導者である主人公ミスター・Aが毎晩のように見る不思議な夢から始まる。その夢の中では、「あるもの」がミスター・Aに「宇宙の一切の秘密と真理を教える代わりに二百二十億の全人類の生命をうばう」という申し出をする。この両者のやり取りが実に知的にスリリングであり、冒頭から、こちらの心の琴線にびんびんと響くわけである。普通の人なら、そんなことのために人命を犠牲にするのは、一名たりともまっぴらごめんだと考えることだろう。いったんはミスター・Aもそう考える。「『知性』が……それほど尚(とうと)いものか」「二百二十億人の、それぞれの人生の中のささやかな幸福を犠牲にするに値するものか……」と。しかし、人間の存在意義について少しでも考えてみたことがある人は共感してくださるのではないかと思うが、人の「知りたいという欲望」は、食欲や性欲には負けるかもしれないが、ある種の人にとってはかなり強烈な部類に入る。小松左京という作家はまさに「旺盛な知識欲」の塊のような人だったし、当然本編のミスター・Aもそのような作家の性格を反映していると見ていい。機転の利く彼は、「あるもの」に対して「宇宙の秘密の代わりに万能の力が欲しい」と切り返すのだ。力を手に入れて宇宙の秘密を手に入れ、奪われた二百二十億人の命を救い、万人にその秘密を教えるのだと。これもまた、死の直前まで民衆の力を信じていた小松らしい答えである。「あるもの」は答えないまま去り、目覚めたミスター・Aの日常が始まっていく。
この後、地球の正体について驚愕の事実が明らかにされ、再度「あるもの」が登場して同じ申し出を繰り返すのだが、このあたりはネタバレになってしまうので詳述はしない。ミスター・Aは申し出を受けるのか受けないのかが物語の焦点となっており、結末で彼はきっぱりと決断を下す。この返事には小松左京という作家のエッセンスが凝縮されているように思う。記憶違いかもしれないが、大学時代の読書会で、誰かが「『すぺるむ・さぴえんすの冒険』には小松左京の全てが詰まっている」と言っていたのをふと思い出した。その時は、そんなものかなあと半信半疑だったのだが、今なら自分も自信を持って言える。ここには確かに小松左京の全てではないにしろ、小松SFの全てが詰まっていると。超越への道を進む者ととどまる者、論理的・知的倫理と情緒的・美的倫理との対立、想定内の事態にしか対応できないシステムに比してそれを超え得る個人の能力への高い信頼、それらを壮大なスケールのもとで描き出す圧倒的なまでの筆力。執筆当時四十代半ば、成熟した小松左京の最良の成果がここにある。
小説的完成度の高い「ゴルディアスの結び目」ばかりが目立っているが、本来は本短編集に含まれる四篇は等価な連作となっており、「すぺるむ・さぴえんす」の結末はそのまま「あなろぐ・らヴ」へとつながっていく。こちらも宇宙的なスケールが感じられる傑作で、宇宙を超えて伝わる「情報」というアイディアにはイーガン『ディアスポラ』につながるものがあると思う。詳しくはまたの機会に。いや、こんな傑作がごろごろしているのだから、やはり小松左京はすごいね、ほんと。
駄文を読んでくださっている皆さま、よいお年をお迎えください。
「すぺるむ・さぴえんすの冒険」は地球の最高指導者である主人公ミスター・Aが毎晩のように見る不思議な夢から始まる。その夢の中では、「あるもの」がミスター・Aに「宇宙の一切の秘密と真理を教える代わりに二百二十億の全人類の生命をうばう」という申し出をする。この両者のやり取りが実に知的にスリリングであり、冒頭から、こちらの心の琴線にびんびんと響くわけである。普通の人なら、そんなことのために人命を犠牲にするのは、一名たりともまっぴらごめんだと考えることだろう。いったんはミスター・Aもそう考える。「『知性』が……それほど尚(とうと)いものか」「二百二十億人の、それぞれの人生の中のささやかな幸福を犠牲にするに値するものか……」と。しかし、人間の存在意義について少しでも考えてみたことがある人は共感してくださるのではないかと思うが、人の「知りたいという欲望」は、食欲や性欲には負けるかもしれないが、ある種の人にとってはかなり強烈な部類に入る。小松左京という作家はまさに「旺盛な知識欲」の塊のような人だったし、当然本編のミスター・Aもそのような作家の性格を反映していると見ていい。機転の利く彼は、「あるもの」に対して「宇宙の秘密の代わりに万能の力が欲しい」と切り返すのだ。力を手に入れて宇宙の秘密を手に入れ、奪われた二百二十億人の命を救い、万人にその秘密を教えるのだと。これもまた、死の直前まで民衆の力を信じていた小松らしい答えである。「あるもの」は答えないまま去り、目覚めたミスター・Aの日常が始まっていく。
この後、地球の正体について驚愕の事実が明らかにされ、再度「あるもの」が登場して同じ申し出を繰り返すのだが、このあたりはネタバレになってしまうので詳述はしない。ミスター・Aは申し出を受けるのか受けないのかが物語の焦点となっており、結末で彼はきっぱりと決断を下す。この返事には小松左京という作家のエッセンスが凝縮されているように思う。記憶違いかもしれないが、大学時代の読書会で、誰かが「『すぺるむ・さぴえんすの冒険』には小松左京の全てが詰まっている」と言っていたのをふと思い出した。その時は、そんなものかなあと半信半疑だったのだが、今なら自分も自信を持って言える。ここには確かに小松左京の全てではないにしろ、小松SFの全てが詰まっていると。超越への道を進む者ととどまる者、論理的・知的倫理と情緒的・美的倫理との対立、想定内の事態にしか対応できないシステムに比してそれを超え得る個人の能力への高い信頼、それらを壮大なスケールのもとで描き出す圧倒的なまでの筆力。執筆当時四十代半ば、成熟した小松左京の最良の成果がここにある。
小説的完成度の高い「ゴルディアスの結び目」ばかりが目立っているが、本来は本短編集に含まれる四篇は等価な連作となっており、「すぺるむ・さぴえんす」の結末はそのまま「あなろぐ・らヴ」へとつながっていく。こちらも宇宙的なスケールが感じられる傑作で、宇宙を超えて伝わる「情報」というアイディアにはイーガン『ディアスポラ』につながるものがあると思う。詳しくはまたの機会に。いや、こんな傑作がごろごろしているのだから、やはり小松左京はすごいね、ほんと。
駄文を読んでくださっている皆さま、よいお年をお迎えください。
小松左京その1(『日本沈没』) ― 2011-12-30 19:38

もうすぐ激動の2011年も終わり。3月の東日本大震災は妹一家が仙台に住んでいるので、他人事ではなかった。話し始めるとキリがないし、本ブログとはあまり関係ない話になるので詳述は差し控えるが、何とか皆無事で心の底から安堵したことだけは書いておこう。自然災害の恐ろしさと原発事故の愚かしさについて考えざるを得ない一年であった。こんなとき、40過ぎ(50近く)のSF者が思い出すのは無論小松左京の『日本沈没』である。
主人公小野寺がコンクリートの壁に見つけるわずか1センチの亀裂から始まるこの物語は、島の水没、死者4,200人の「京都大地震」、マグニチュード8.5の大地震と津波が東京を直撃し、死者200万人を超える大災害となった「第二次関東大震災」と、加速度的に勢いが増していく災害を圧倒的な筆力で、読者の息をつかせる間もなく次々と描き出していくことによって、日本の沈没という途方もない出来事に見事なまでのリアリティをもたらすことに成功している。このリアリティって、結局冒頭の「1センチの亀裂」に鍵があると思うんだよね。針の穴のような小さな一点から巨大なダムの壁が崩壊に至るダイナミズム。これをきちんとプレートテクトニクスや、堀晃も絶賛している架空理論「ナカタ過程」を駆使して理詰めで見せてくれているから、「1センチの亀裂」という現象を認識するのと同様に「日本が沈没するという事実」を読者は納得できるわけである。逆に言えば、「日本沈没」は「わずか1センチの亀裂」に凝縮されている。筆者が偏愛する傑作ジュブナイル『青い宇宙の冒険』の冒頭に登場する「ねじれ松」が「時空間の歪み」をくっきりと浮かび上がらせていたように。壮大な嘘を小さな具象の演繹で表す。ここにSFの本質があることは言うまでもない。
小学5年の初読以来、本書を読むのはこれで3度めになると思うが、その度に新たな発見があり、小松左京の偉大さを再認識させられた。多くのSFファン同様、7月の小松左京の死去以来何冊かの著作を読み返し、そして思ったのだが、氏の情景描写の巧さはもっと評価されて然るべきではないだろうか。『日本沈没』における地震の描写はもちろんのこと、『果しなき流れの果に』のラストにおける庭の描写(連載時には一切なく、単行本化で加筆された部分。何度読んでもここで感動してしまうのは筆者だけ?)、「流れる女」における古都の描写など、鮮やかに情景が目に浮かんでくる場面がいくつもある。それは作家の基礎体力さ、と言って済ますには惜しいと思うのだ。小松左京が亡き今こそ、氏の作品を繰り返し読んで、味わい、深く考えること。それこそが残された我々読者が果たすべき使命であろう。
主人公小野寺がコンクリートの壁に見つけるわずか1センチの亀裂から始まるこの物語は、島の水没、死者4,200人の「京都大地震」、マグニチュード8.5の大地震と津波が東京を直撃し、死者200万人を超える大災害となった「第二次関東大震災」と、加速度的に勢いが増していく災害を圧倒的な筆力で、読者の息をつかせる間もなく次々と描き出していくことによって、日本の沈没という途方もない出来事に見事なまでのリアリティをもたらすことに成功している。このリアリティって、結局冒頭の「1センチの亀裂」に鍵があると思うんだよね。針の穴のような小さな一点から巨大なダムの壁が崩壊に至るダイナミズム。これをきちんとプレートテクトニクスや、堀晃も絶賛している架空理論「ナカタ過程」を駆使して理詰めで見せてくれているから、「1センチの亀裂」という現象を認識するのと同様に「日本が沈没するという事実」を読者は納得できるわけである。逆に言えば、「日本沈没」は「わずか1センチの亀裂」に凝縮されている。筆者が偏愛する傑作ジュブナイル『青い宇宙の冒険』の冒頭に登場する「ねじれ松」が「時空間の歪み」をくっきりと浮かび上がらせていたように。壮大な嘘を小さな具象の演繹で表す。ここにSFの本質があることは言うまでもない。
小学5年の初読以来、本書を読むのはこれで3度めになると思うが、その度に新たな発見があり、小松左京の偉大さを再認識させられた。多くのSFファン同様、7月の小松左京の死去以来何冊かの著作を読み返し、そして思ったのだが、氏の情景描写の巧さはもっと評価されて然るべきではないだろうか。『日本沈没』における地震の描写はもちろんのこと、『果しなき流れの果に』のラストにおける庭の描写(連載時には一切なく、単行本化で加筆された部分。何度読んでもここで感動してしまうのは筆者だけ?)、「流れる女」における古都の描写など、鮮やかに情景が目に浮かんでくる場面がいくつもある。それは作家の基礎体力さ、と言って済ますには惜しいと思うのだ。小松左京が亡き今こそ、氏の作品を繰り返し読んで、味わい、深く考えること。それこそが残された我々読者が果たすべき使命であろう。
最近のコメント