三上延『ビブリア古書堂の事件手帖5』 ― 2014-04-28 00:57

1月発売の本。もちろん発売後すぐ読んではいるのだが、書評をしばらくさぼっていたので今さら取り上げることをご容赦願いたい。4巻が江戸川乱歩を扱って首尾一貫したストーリイを保っていたのに対し、今回は、『彷書月刊』、手塚治虫『ブラックジャック』、寺山修司『われに五月を』の三点にまつわる事件を扱っており、当初の構成に戻った感じである。『彷書月刊』事件では、お馴染みの登場人物、せどり屋志田の過去が明らかになり、『ブラックジャック』事件では、妻が危篤状態の際に取った夫の奇妙な行動(『ブラックジャック』4巻の初版を古書店で購入した)の謎を解き、『われに五月を』事件では、栞子の母智恵子も絡んだ、寺山修司直筆原稿が消しゴムで消されてしまった事件の真相が明かされる。いずれの事件にも共通しているのは、家族間の感情のもつれを栞子が解決していくという構図である。『たんぽぽ娘』のときから思っているのだが、この家族間の感情のもつれと本との関わりがちょっと強引というか作為的過ぎるというか、無理があるという印象は変わらない。しかし、それにもかかわらず、ぐいぐい読まされて結局物語に感動させられてしまうのは、作者の、書物の内容への深い理解と書物という物質的な存在へのこだわりが尋常ではないからだ。私はこのシリーズを、物語の形をとった風変わりな書評として読んでいる。
「もしこの世界にあるものが現実だけだったら、物語というものが存在しなかったら、わたしたちの人生はあまりにも貧しすぎる……現実を実り多いものにするために、わたしたちは物語を読むんです」(本書186ページ)
という栞子の言葉には、本を愛する者だったら、誰しも素直に共感するだろう。本書をきっかけに新たに『ブラックジャック』や寺山修司を読んでみよう(再読してみよう)と思う人が出てくれば、それは書評としての効用があったということだ。私も今回は思わずダンボール箱の中から少年チャンピオンコミックスの『ブラックジャック』4巻を引っ張り出して読みふけってしまった。年齢からして、家にあるのは、当然「植物人間」の入った版(1976年11月15版)である。そうかあ、これが今は読めないんだと思いながら懐かしく読んだ。次はどんな本が登場するのか、もちろん肝心の物語、太宰治『晩年』事件の続きも含めて、楽しみである。
「もしこの世界にあるものが現実だけだったら、物語というものが存在しなかったら、わたしたちの人生はあまりにも貧しすぎる……現実を実り多いものにするために、わたしたちは物語を読むんです」(本書186ページ)
という栞子の言葉には、本を愛する者だったら、誰しも素直に共感するだろう。本書をきっかけに新たに『ブラックジャック』や寺山修司を読んでみよう(再読してみよう)と思う人が出てくれば、それは書評としての効用があったということだ。私も今回は思わずダンボール箱の中から少年チャンピオンコミックスの『ブラックジャック』4巻を引っ張り出して読みふけってしまった。年齢からして、家にあるのは、当然「植物人間」の入った版(1976年11月15版)である。そうかあ、これが今は読めないんだと思いながら懐かしく読んだ。次はどんな本が登場するのか、もちろん肝心の物語、太宰治『晩年』事件の続きも含めて、楽しみである。
施川ユウキ『バーナード嬢曰く。』 ― 2013-06-02 23:34

朝日新聞の南信長のレビューを読んで読みたくなり、アマゾンに注文したら品切れ。待つこと数週間、ようやく2日前に届いたので早速読む。いや、これは期待に違わず面白かった。
図書館で本を読むふりをして自分を読書家であるかのように見せかける女子高生町田さわ子(自称バーナード嬢)と、彼女を見つめる本当の読書家男子高生、さらにそれを見つめる図書委員の女子高生とが繰り広げる本に関するささやかなドラマ。のはずだったのだが、そこにSFファンの女子高生神林しおりが登場。彼女が開陳するマニアックな知識とこだわりが爆発する個所は、これはもう一般読者をはるかに超えて、SFマニアのための爆笑エッセイと化している。お薦めのSFを一冊と言われたり、SFの定義を聞かれたりしたときに、彼女がえんえんと悩むところや、タイトルにこだわったり、ジュヴナイルSFのちょっとしたところにこだわったりするところなど、見事にSFファンのツボを押さえており、そうそう、こんなことあるよなあと思わずにはいられない。ネットでも話題になっていたが、イーガンはよくわからなくてもいいんだというあたりは、特に理屈に力が入っており読み応え十分。
SF以外でも面白いところがたくさんあるし、基本的に本に対する愛があふれているので、紙媒体としての本が好きな人にはとにかくお薦めである。
図書館で本を読むふりをして自分を読書家であるかのように見せかける女子高生町田さわ子(自称バーナード嬢)と、彼女を見つめる本当の読書家男子高生、さらにそれを見つめる図書委員の女子高生とが繰り広げる本に関するささやかなドラマ。のはずだったのだが、そこにSFファンの女子高生神林しおりが登場。彼女が開陳するマニアックな知識とこだわりが爆発する個所は、これはもう一般読者をはるかに超えて、SFマニアのための爆笑エッセイと化している。お薦めのSFを一冊と言われたり、SFの定義を聞かれたりしたときに、彼女がえんえんと悩むところや、タイトルにこだわったり、ジュヴナイルSFのちょっとしたところにこだわったりするところなど、見事にSFファンのツボを押さえており、そうそう、こんなことあるよなあと思わずにはいられない。ネットでも話題になっていたが、イーガンはよくわからなくてもいいんだというあたりは、特に理屈に力が入っており読み応え十分。
SF以外でも面白いところがたくさんあるし、基本的に本に対する愛があふれているので、紙媒体としての本が好きな人にはとにかくお薦めである。
今日マチ子『U』 ― 2013-05-26 21:30
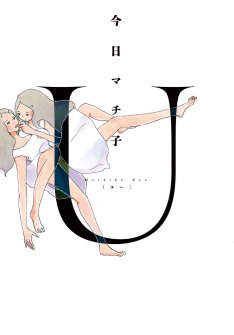
今日マチ子の作品は、雑誌「ダ・ヴィンチ」に載っていた百人一首を現代風に解釈して1ページの漫画に再構成したものしか読んだことがなかった。絵柄が柔らかく、繊細で、淡い水彩画のようなタッチで描かれており、印象に残った。何気ない日常を切り取って描くことが上手い漫画家なんだろうなと勝手に思っていたので、本屋で何気なく手にとり買ってきた本書を読んでびっくり。こんなかわいい絵柄で、こんな残酷な話を描くなんて。
クローン技術で人間の舌を再生し、それをゼリーに差しこむことによってコピー人間を作る研究をしている教授とその助手。助手はそこそこの美人で、でも恋愛には奥手というよくある設定だ。助手をもとに作られたコピー人間が徐々にオリジナルを憎むようになり、ついに惨劇が起きる……。このクローン技術は全くリアリティがないので、SFとしては完全に破綻している。しかし、舌をゼリーに差しこんでコピーができるというイメージの深さは、一概にばかばかしいと切って捨てられないものがある。直接的にエロティックなシーンはほとんどないにもかかわらず、エロスを感じさせる作品になっているのは、この「舌」へのこだわりがあるからだろう。殺人あり、カンニバリズムありという結構ハードな展開なのだが、さらりと描いてあるので、それがかえって怖いという余情表現の効果もあるね。他の長編も読んでみたいという気にさせられた。
クローン技術で人間の舌を再生し、それをゼリーに差しこむことによってコピー人間を作る研究をしている教授とその助手。助手はそこそこの美人で、でも恋愛には奥手というよくある設定だ。助手をもとに作られたコピー人間が徐々にオリジナルを憎むようになり、ついに惨劇が起きる……。このクローン技術は全くリアリティがないので、SFとしては完全に破綻している。しかし、舌をゼリーに差しこんでコピーができるというイメージの深さは、一概にばかばかしいと切って捨てられないものがある。直接的にエロティックなシーンはほとんどないにもかかわらず、エロスを感じさせる作品になっているのは、この「舌」へのこだわりがあるからだろう。殺人あり、カンニバリズムありという結構ハードな展開なのだが、さらりと描いてあるので、それがかえって怖いという余情表現の効果もあるね。他の長編も読んでみたいという気にさせられた。
諫早創『進撃の巨人』 ― 2013-05-25 02:52
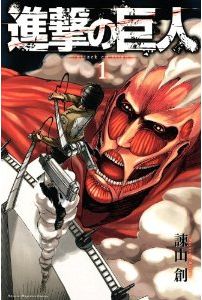
中間考査も終わり、生徒も重圧から解き放たれて伸び伸びと活動している。今日は校内で二本の棒を手にして振り回しながらジャンプしている女子高生を見かけたが、「イェーガー」などと叫んでいたので、あれはおそらく『進撃の巨人』ごっこをして遊んでいたのであろう(どんな学校だと思われるかもしれないが、いわゆる普通の進学校である)。
このように、一部生徒の間で人気の高い『巨人』であるが、決して軽い作品ではなく、読後感はかなり重い。陰鬱で残酷な描写も多数あり、万人向けの漫画とは言い難い。アニメーションになると聞いたときは、え? ホントにやるのといった驚きがあった。きちんと全部観ているわけではないが、数話観た限りでは、原作に忠実に作られており、作画、背景も丁寧でクォリティは高い。この出来栄えなら原作のファンも納得するだろう。
正体不明の巨人から逃れて、壁の中に閉じこもって暮らす人間たちの前に再び巨人が襲いかかる。巨人たちの目的はただ一つ、人間をむさぼり食うことだ。巨人を倒すにはうなじの肉を素早く的確にそぎ落とすしかない。ガスを燃料とした立体起動装置を駆使して巨人に立ち向かう調査兵団の若き兵士たちが本書の主役である。訓練および実戦を通じて苦難を乗り越えていく彼らの姿が描かれるという大筋だけ見ると普通の少年マンガなのだが、その苦難が並大抵のものではない。グロテスクな巨人に仲間が次々と食われていくという凄惨な場面には、思わず目を背けたくなる。非力な自分だけでは過酷な運命には逆らえない、どうにもならないという閉塞感、無力感は、グローバル社会の中で強烈な競争にさらされている若者にとってリアルな実感なのだろう。巨人とは、現実社会の隠喩でもあると分析するのはたやすいことだ。
しかし、作者は「人類対巨人=若者対現実社会」という単純な図式を周到にずらしていく。主人公エレン・イェーガーは医師である父に何らかの処置を施された結果、自らの意志で巨人になれる能力を獲得しており、巨人と人間を繋ぐ存在となっている。ただし、巨人になったときには自らの意志を制御できず味方を攻撃したりするので、意識や知性は抑圧されている。巨人化したエレンは無意識的な破壊衝動、野獣的な生存本能を体現した存在なのだ。過酷な現実社会、すなわち自らの外部を象徴していたはずの巨人と、自らの内部を象徴する巨人とが戦ううちに、両者が入り混じり、違いが徐々に無化されていく。ネタばれになってしまうので詳しくは書けないが、敵だと思っていたらそれが仲間だったり、仲間が敵になったりという十巻までの展開は、「人類対巨人」の図式を「人類=巨人」へと移行していくかなりスリリングな試みとなっている。特に十巻のラストには、おいおい、いくらなんでもそれはないだろうと驚愕させられた。この先がどう展開していくのか、ちょっと目が離せない作品である。
このように、一部生徒の間で人気の高い『巨人』であるが、決して軽い作品ではなく、読後感はかなり重い。陰鬱で残酷な描写も多数あり、万人向けの漫画とは言い難い。アニメーションになると聞いたときは、え? ホントにやるのといった驚きがあった。きちんと全部観ているわけではないが、数話観た限りでは、原作に忠実に作られており、作画、背景も丁寧でクォリティは高い。この出来栄えなら原作のファンも納得するだろう。
正体不明の巨人から逃れて、壁の中に閉じこもって暮らす人間たちの前に再び巨人が襲いかかる。巨人たちの目的はただ一つ、人間をむさぼり食うことだ。巨人を倒すにはうなじの肉を素早く的確にそぎ落とすしかない。ガスを燃料とした立体起動装置を駆使して巨人に立ち向かう調査兵団の若き兵士たちが本書の主役である。訓練および実戦を通じて苦難を乗り越えていく彼らの姿が描かれるという大筋だけ見ると普通の少年マンガなのだが、その苦難が並大抵のものではない。グロテスクな巨人に仲間が次々と食われていくという凄惨な場面には、思わず目を背けたくなる。非力な自分だけでは過酷な運命には逆らえない、どうにもならないという閉塞感、無力感は、グローバル社会の中で強烈な競争にさらされている若者にとってリアルな実感なのだろう。巨人とは、現実社会の隠喩でもあると分析するのはたやすいことだ。
しかし、作者は「人類対巨人=若者対現実社会」という単純な図式を周到にずらしていく。主人公エレン・イェーガーは医師である父に何らかの処置を施された結果、自らの意志で巨人になれる能力を獲得しており、巨人と人間を繋ぐ存在となっている。ただし、巨人になったときには自らの意志を制御できず味方を攻撃したりするので、意識や知性は抑圧されている。巨人化したエレンは無意識的な破壊衝動、野獣的な生存本能を体現した存在なのだ。過酷な現実社会、すなわち自らの外部を象徴していたはずの巨人と、自らの内部を象徴する巨人とが戦ううちに、両者が入り混じり、違いが徐々に無化されていく。ネタばれになってしまうので詳しくは書けないが、敵だと思っていたらそれが仲間だったり、仲間が敵になったりという十巻までの展開は、「人類対巨人」の図式を「人類=巨人」へと移行していくかなりスリリングな試みとなっている。特に十巻のラストには、おいおい、いくらなんでもそれはないだろうと驚愕させられた。この先がどう展開していくのか、ちょっと目が離せない作品である。
萩尾望都作品集『なのはな』 ― 2012-03-13 22:20

3月12日発行の萩尾望都の漫画最新刊。あちこちで話題になっている「プルート夫人」など、放射性物質を擬人化して描いた三部作を始め、原発事故に関連した作品五編を収録した単行本である。三巻まで刊行されている短編シリーズ「ここではない★どこか」に属してはいるが、今までの新書版ではなく、ハードカバーでの刊行、表紙も箔押しの丁寧な造本であり、小学館の本気具合がうかがわれる。
前回レビューした対談集でも「プルート夫人」については触れられていた。気熱をやってもらった後、体中のパーツがガシッとつながった感じになり、3時間でネームができてしまったのだという。なるほど、プルトニウムを妖艶な女性として登場させ、彼女に翻弄される男性達の情けなさを流れるような筆致で描いた本作は、近年の萩尾望都の淡々とした作品群の中では異様とも言える迫力に満ちている。逆にウランを気品あふれる貴公子として登場させ、彼の魅力に参ってしまう女性達を描いた「雨の音―ウラノス伯爵―」、再度プルトニウムをサロメとして登場させ、今度はプルトニウムの内面に入り込んでその恐ろしさを描いた「サロメ20××」と続けて読んでいくと、311の刺激が、萩尾望都の創作意欲に火をつけてしまった様子がよくわかる。どれも一気に読ませるパワーが感じられるのだ。読んでいるうちに、そう言えば、萩尾望都には社会問題を扱った作品が過去にもあったぞと思い出した。公害問題を描いた「かたっぽのふるぐつ」だ。ゆうという少年が喘息で死んでしまう話で、重い読後感を残す異色作だった。こんな作品まですらすら浮かんでくるとは、さすが人生で大切なことは萩尾望都で学んだ自分である(自画自賛)。『ポー』や『トーマ』のファンからしたら意外に思われるかもしれないが、もともと萩尾望都には社会的意識の強いところがあったのではないか。というか、萩尾望都っていうのは、何気ない日常を描くのが無茶苦茶上手い一方で、世界が日常だけでは成り立っていないということ、日常に裂け目が入り、非日常を垣間見せるその瞬間を作品に昇華させるのが実に上手い作家でもある。現実が非日常をもたらした311に対して、作品化せずにはいられなかったというのが正直なところなのだろう。
派手な「プルート夫人」もいいけれど、チェルノブイリとフクシマを重ねて描いた表題作「なのはな」が実は一番傑作。1200円は少々高いかもしれないが、買って損のない一冊である。
前回レビューした対談集でも「プルート夫人」については触れられていた。気熱をやってもらった後、体中のパーツがガシッとつながった感じになり、3時間でネームができてしまったのだという。なるほど、プルトニウムを妖艶な女性として登場させ、彼女に翻弄される男性達の情けなさを流れるような筆致で描いた本作は、近年の萩尾望都の淡々とした作品群の中では異様とも言える迫力に満ちている。逆にウランを気品あふれる貴公子として登場させ、彼の魅力に参ってしまう女性達を描いた「雨の音―ウラノス伯爵―」、再度プルトニウムをサロメとして登場させ、今度はプルトニウムの内面に入り込んでその恐ろしさを描いた「サロメ20××」と続けて読んでいくと、311の刺激が、萩尾望都の創作意欲に火をつけてしまった様子がよくわかる。どれも一気に読ませるパワーが感じられるのだ。読んでいるうちに、そう言えば、萩尾望都には社会問題を扱った作品が過去にもあったぞと思い出した。公害問題を描いた「かたっぽのふるぐつ」だ。ゆうという少年が喘息で死んでしまう話で、重い読後感を残す異色作だった。こんな作品まですらすら浮かんでくるとは、さすが人生で大切なことは萩尾望都で学んだ自分である(自画自賛)。『ポー』や『トーマ』のファンからしたら意外に思われるかもしれないが、もともと萩尾望都には社会的意識の強いところがあったのではないか。というか、萩尾望都っていうのは、何気ない日常を描くのが無茶苦茶上手い一方で、世界が日常だけでは成り立っていないということ、日常に裂け目が入り、非日常を垣間見せるその瞬間を作品に昇華させるのが実に上手い作家でもある。現実が非日常をもたらした311に対して、作品化せずにはいられなかったというのが正直なところなのだろう。
派手な「プルート夫人」もいいけれど、チェルノブイリとフクシマを重ねて描いた表題作「なのはな」が実は一番傑作。1200円は少々高いかもしれないが、買って損のない一冊である。
最近のコメント