三上延『ビブリア古書堂の事件手帖5』 ― 2014-04-28 00:57

1月発売の本。もちろん発売後すぐ読んではいるのだが、書評をしばらくさぼっていたので今さら取り上げることをご容赦願いたい。4巻が江戸川乱歩を扱って首尾一貫したストーリイを保っていたのに対し、今回は、『彷書月刊』、手塚治虫『ブラックジャック』、寺山修司『われに五月を』の三点にまつわる事件を扱っており、当初の構成に戻った感じである。『彷書月刊』事件では、お馴染みの登場人物、せどり屋志田の過去が明らかになり、『ブラックジャック』事件では、妻が危篤状態の際に取った夫の奇妙な行動(『ブラックジャック』4巻の初版を古書店で購入した)の謎を解き、『われに五月を』事件では、栞子の母智恵子も絡んだ、寺山修司直筆原稿が消しゴムで消されてしまった事件の真相が明かされる。いずれの事件にも共通しているのは、家族間の感情のもつれを栞子が解決していくという構図である。『たんぽぽ娘』のときから思っているのだが、この家族間の感情のもつれと本との関わりがちょっと強引というか作為的過ぎるというか、無理があるという印象は変わらない。しかし、それにもかかわらず、ぐいぐい読まされて結局物語に感動させられてしまうのは、作者の、書物の内容への深い理解と書物という物質的な存在へのこだわりが尋常ではないからだ。私はこのシリーズを、物語の形をとった風変わりな書評として読んでいる。
「もしこの世界にあるものが現実だけだったら、物語というものが存在しなかったら、わたしたちの人生はあまりにも貧しすぎる……現実を実り多いものにするために、わたしたちは物語を読むんです」(本書186ページ)
という栞子の言葉には、本を愛する者だったら、誰しも素直に共感するだろう。本書をきっかけに新たに『ブラックジャック』や寺山修司を読んでみよう(再読してみよう)と思う人が出てくれば、それは書評としての効用があったということだ。私も今回は思わずダンボール箱の中から少年チャンピオンコミックスの『ブラックジャック』4巻を引っ張り出して読みふけってしまった。年齢からして、家にあるのは、当然「植物人間」の入った版(1976年11月15版)である。そうかあ、これが今は読めないんだと思いながら懐かしく読んだ。次はどんな本が登場するのか、もちろん肝心の物語、太宰治『晩年』事件の続きも含めて、楽しみである。
「もしこの世界にあるものが現実だけだったら、物語というものが存在しなかったら、わたしたちの人生はあまりにも貧しすぎる……現実を実り多いものにするために、わたしたちは物語を読むんです」(本書186ページ)
という栞子の言葉には、本を愛する者だったら、誰しも素直に共感するだろう。本書をきっかけに新たに『ブラックジャック』や寺山修司を読んでみよう(再読してみよう)と思う人が出てくれば、それは書評としての効用があったということだ。私も今回は思わずダンボール箱の中から少年チャンピオンコミックスの『ブラックジャック』4巻を引っ張り出して読みふけってしまった。年齢からして、家にあるのは、当然「植物人間」の入った版(1976年11月15版)である。そうかあ、これが今は読めないんだと思いながら懐かしく読んだ。次はどんな本が登場するのか、もちろん肝心の物語、太宰治『晩年』事件の続きも含めて、楽しみである。
殊能将之訃報 ― 2013-03-31 21:40
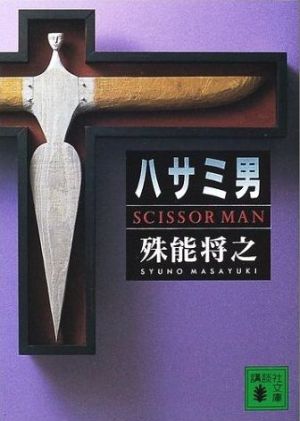
大学時代からの友人であるミステリ作家の殊能将之が亡くなったとの知らせが昨日(3月30日)ネットを駆け巡った。亡くなったのは2月11日であり、自分が友人から知らせを聞いたのが2月22日。最初は呆然とし、それからじわじわと悲しみが広がってきたのだが、伏せていなければならないので、何とも言えない中途半端な気持ちがずっとくすぶっていた。思いを吐き出したいのだが、吐き出せないといったもどかしさ。4月3日発売のメフィストに追悼記事が載るとのことで、30日なら友人に話してもいいだろうと、東京に住む大学時代の友人たちと会う約束をし、仕事が忙しい中、無理やり時間を作って新幹線に飛び乗って、東京に向かっている最中に、ネットに流れたらしい。
知ってからは、ずっと著作を読み返していた。間違いなくミステリ界の歴史に残るであろう『ハサミ男』、石動戯作初登場、自分も刑事役で出演させてもらったのが印象深い『美濃牛』、ミステリ・ファンの度肝を抜いた『黒い仏』、水城初登場で、殊能作品にしては珍しく最後にほろりとさせられる『鏡の中は日曜日』、中世の視点で東京を眺めたところが斬新な『キマイラの新しい城』、どれも傑作でありながら、ひとつとして同じ趣向の作品がない。まとめて読み返して、本当にすごいと思った。
しかし、これは実は氏のすべてではない。彼の該博な知識、人を引き付けずにはおれない語り口、切れ味鋭い論理的思考力、それはまだまだ、これから存分に発揮されていくべきものだった。彼を知る者すべてが、そう思っていたはずだ。もっともっと書いてほしかった。いや、生きていてほしかった。もうあの、時には毒舌で皮肉たっぷりのジョークを聞くこともないのだと思うと、限りなく悔しく、そして悲しい。
一晩、友人たちと彼の思い出を語り合い、大学時代に書かれたレビューなどもまとめて残しておきたいねと話した。ちょうど今年の夏、名大SF研30周年行事を行うので、本当はそこに呼ぼうと思っていたのだが……。もう何を言っても仕方がない。
翌日、古本屋でも回って帰ろうと思い、いつものように、神保町を歩いて「@ワンダー」の中に入った。その瞬間、馴染みのある曲が耳に入ってきた。店内に流れていたのは……XTC……これは……そう、「ハサミ男(Scissor Man)」じゃないか! 数冊の本を手にしてレジに向かう。聞くべきか、そのまま出ていくべきか。レジには年配のおじさんと20代と思しき若者の二人がいる。どちらがXTCをかけているのか。レジをすませたが、結局話しかける勇気が出ない。ちょうど若者の方が休憩のため外へ出ていく。意を決して私は話しかけた。「この曲をかけているのはどなたでしょうか」
「私ですが…」けげんそうに若者が答える。
「XTCですよね。何か理由があるんですか」
「好きなんです。実は昨日…殊能将之というミステリ作家が亡くなったのを知って…」
「ええ……『ハサミ男』ですよね」
「そうです、大好きな作家だったので、昨日からショックで何も手につかなくて……」
思わず、自分は殊能将之の友人であること、本当に悲しく思っていることを語ってしまった。見も知らぬ古本屋の店員に話すことではないだろうと思ったが、止まらなかった。
若者と別れ、帰途に着く。
なぜか、嬉しさが込み上げてきた。殊能将之は確かに人々の心に残っている。こんなに愛されているんだ……そう思った瞬間だった。彼の死を知ってから、一度も流れなかった涙があふれてきた。神保町から水道橋へ向かう途中、歩きながら私は泣いていた。そこが、数十年前、かつて東京に住んでいた殊能氏とともに歩いた道でもあったことに気づくのに、そう時間はかからなかった……。
知ってからは、ずっと著作を読み返していた。間違いなくミステリ界の歴史に残るであろう『ハサミ男』、石動戯作初登場、自分も刑事役で出演させてもらったのが印象深い『美濃牛』、ミステリ・ファンの度肝を抜いた『黒い仏』、水城初登場で、殊能作品にしては珍しく最後にほろりとさせられる『鏡の中は日曜日』、中世の視点で東京を眺めたところが斬新な『キマイラの新しい城』、どれも傑作でありながら、ひとつとして同じ趣向の作品がない。まとめて読み返して、本当にすごいと思った。
しかし、これは実は氏のすべてではない。彼の該博な知識、人を引き付けずにはおれない語り口、切れ味鋭い論理的思考力、それはまだまだ、これから存分に発揮されていくべきものだった。彼を知る者すべてが、そう思っていたはずだ。もっともっと書いてほしかった。いや、生きていてほしかった。もうあの、時には毒舌で皮肉たっぷりのジョークを聞くこともないのだと思うと、限りなく悔しく、そして悲しい。
一晩、友人たちと彼の思い出を語り合い、大学時代に書かれたレビューなどもまとめて残しておきたいねと話した。ちょうど今年の夏、名大SF研30周年行事を行うので、本当はそこに呼ぼうと思っていたのだが……。もう何を言っても仕方がない。
翌日、古本屋でも回って帰ろうと思い、いつものように、神保町を歩いて「@ワンダー」の中に入った。その瞬間、馴染みのある曲が耳に入ってきた。店内に流れていたのは……XTC……これは……そう、「ハサミ男(Scissor Man)」じゃないか! 数冊の本を手にしてレジに向かう。聞くべきか、そのまま出ていくべきか。レジには年配のおじさんと20代と思しき若者の二人がいる。どちらがXTCをかけているのか。レジをすませたが、結局話しかける勇気が出ない。ちょうど若者の方が休憩のため外へ出ていく。意を決して私は話しかけた。「この曲をかけているのはどなたでしょうか」
「私ですが…」けげんそうに若者が答える。
「XTCですよね。何か理由があるんですか」
「好きなんです。実は昨日…殊能将之というミステリ作家が亡くなったのを知って…」
「ええ……『ハサミ男』ですよね」
「そうです、大好きな作家だったので、昨日からショックで何も手につかなくて……」
思わず、自分は殊能将之の友人であること、本当に悲しく思っていることを語ってしまった。見も知らぬ古本屋の店員に話すことではないだろうと思ったが、止まらなかった。
若者と別れ、帰途に着く。
なぜか、嬉しさが込み上げてきた。殊能将之は確かに人々の心に残っている。こんなに愛されているんだ……そう思った瞬間だった。彼の死を知ってから、一度も流れなかった涙があふれてきた。神保町から水道橋へ向かう途中、歩きながら私は泣いていた。そこが、数十年前、かつて東京に住んでいた殊能氏とともに歩いた道でもあったことに気づくのに、そう時間はかからなかった……。
高野和明『ジェノサイド』 ― 2012-02-13 21:02

『SFが読みたい! 2012年版』でも6位に入っており、アンビの新年会でも話題になっていたので読んでみた。
死んだ父親が研究していた新薬をめぐる陰謀に巻き込まれた大学院生の物語と、アフリカ奥地でウィルスに感染した部族を撲滅する任務を帯びた傭兵の物語とが交錯し、人類の未来に関するヴィジョンも描かれるという壮大なストーリイとなっている。薬物に関する理論や軍事兵器などは入念にリサーチされており、特に、新薬開発の過程などは、なるほどこうやって薬というのは作られていくのかと興味深く読むことができた。後はハイズマン博士が書いた架空論文「人類の絶滅要因の研究と政策への提言(通称ハイズマン・レポート)」がよく作り込まれていて面白い。こうした設定をきちんと積み重ねているので、物語に圧倒的なリアリティが生じるわけである。
タイトルの「ジェノサイド」は、直接的には、傭兵の使命となったアフリカ奥地のピグミー族虐殺を指すと思われるが、それに人類が繰り返してきた集団虐殺(アウシュヴィッツへの言及あり)を重ね合わせ、さらにもうひとひねりSF的な展開を加えた三重の意味があり、象徴的なタイトルにはなっている。エンターテイメントとしての完成度は高い。しかし、SFファンとしての立場から敢えて言うならば、やはりこの物語の結末から始まる物語をこそ読みたいと思う。
アフリカ・パートの過激な描写と日本パートのぬるま湯的な描写の対比は意図されたものだとは思うが、典型的な巻き込まれ型キャラである日本の大学院生の描き方が平板で魅力に乏しいのもどうかと思う。こうでないと今の若者が共感できる作品にならないのかな。まあでも、アフリカ・パートの迫力に圧倒されたのは事実なので、作者の筆力があるのは確か。後はもう少し想像力の翼を広げてほしい、哲学的な深みもほしいというのは、ないものねだりなのだろうか。
死んだ父親が研究していた新薬をめぐる陰謀に巻き込まれた大学院生の物語と、アフリカ奥地でウィルスに感染した部族を撲滅する任務を帯びた傭兵の物語とが交錯し、人類の未来に関するヴィジョンも描かれるという壮大なストーリイとなっている。薬物に関する理論や軍事兵器などは入念にリサーチされており、特に、新薬開発の過程などは、なるほどこうやって薬というのは作られていくのかと興味深く読むことができた。後はハイズマン博士が書いた架空論文「人類の絶滅要因の研究と政策への提言(通称ハイズマン・レポート)」がよく作り込まれていて面白い。こうした設定をきちんと積み重ねているので、物語に圧倒的なリアリティが生じるわけである。
タイトルの「ジェノサイド」は、直接的には、傭兵の使命となったアフリカ奥地のピグミー族虐殺を指すと思われるが、それに人類が繰り返してきた集団虐殺(アウシュヴィッツへの言及あり)を重ね合わせ、さらにもうひとひねりSF的な展開を加えた三重の意味があり、象徴的なタイトルにはなっている。エンターテイメントとしての完成度は高い。しかし、SFファンとしての立場から敢えて言うならば、やはりこの物語の結末から始まる物語をこそ読みたいと思う。
アフリカ・パートの過激な描写と日本パートのぬるま湯的な描写の対比は意図されたものだとは思うが、典型的な巻き込まれ型キャラである日本の大学院生の描き方が平板で魅力に乏しいのもどうかと思う。こうでないと今の若者が共感できる作品にならないのかな。まあでも、アフリカ・パートの迫力に圧倒されたのは事実なので、作者の筆力があるのは確か。後はもう少し想像力の翼を広げてほしい、哲学的な深みもほしいというのは、ないものねだりなのだろうか。
米澤穂信『折れた竜骨』 ― 2012-01-09 23:13

このミス昨年ベスト2。アンビ新年会でも話題になっていたので、早速読んでみた。十二世紀末のイングランド、ブリテン島の東にある小さな架空の島、ソロン島に舞台をとり、魔術師や魔法が存在する世界における殺人事件を取り扱った異色ミステリである。SFファン、ファンタジイ・ファンから見ると、ランドル・ギャレット『魔術師が多すぎる』やピアズ・アンソニイの《ザンス》シリーズなどでロジカルに魔法が存在するという設定は馴染み深いものがあるが、国内ミステリにおいては随分と思い切った設定と言えるだろう。
北海交易を一手に制したエイルウィン家の当主、ローレント・エイルウィンののところへ傭兵が集まってくる場面から物語は始まる。どうやら、彼は近々恐るべき敵であるデーン人の襲撃があると考えているらしい。ブレーメンの騎士、ウエールズの弓手、マジャル人の女性、サラセン人の魔術師など、様々な者が集められ、当主との面会を果たすが、その晩彼は殺されてしまうのだ。一体誰が、何のために……? 事件を追うのは聖アンブロジウス病院兄弟団の騎士ファルクとその従者ニコラ。ローレントの娘アミーナが語り手の役を担う。犯人は魔術を使って〈走狗〉と呼ばれる身代わりを使いローレントを殺させたらしい。〈走狗〉はその後自分のしたことを忘れてしまうので、下手人捜しは至難の業である。しかし、ファルクは決然と言う。「たとえ誰かが魔術師であったとしても、また誰がどのような魔術を用いたとしても、それでも〈走狗〉は彼である、または彼ではない、という理由を見つけ出すのだ」と。ここに本書が本格ミステリとして成立している根拠がある。本書においては、魔法と言っても、厳然として作られたルールに縛られており、それに則って論理的に考えていけば、事件の解決に至るのだ。決してルールからはみ出したり、ルール自体を疑うこともなく、作品は見事に完結する。面白いことは面白いのだが、まあ、よくできたパズルみたいなもので、それ以上の深みがあるわけではない。語り手であるアミーナを始め、探偵役のファルクとニコラ、どのキャラクターも平板で、ちょっと物足りない気がする。知的遊戯としては十分及第点なのだが……。
このミス上位にこのような作品が来るというのは少し驚きではある。綾辻行人ら新本格の登場のような衝撃はないけれど、こうして世代交代というのはゆるやかに進んでいくのかもしれない。
北海交易を一手に制したエイルウィン家の当主、ローレント・エイルウィンののところへ傭兵が集まってくる場面から物語は始まる。どうやら、彼は近々恐るべき敵であるデーン人の襲撃があると考えているらしい。ブレーメンの騎士、ウエールズの弓手、マジャル人の女性、サラセン人の魔術師など、様々な者が集められ、当主との面会を果たすが、その晩彼は殺されてしまうのだ。一体誰が、何のために……? 事件を追うのは聖アンブロジウス病院兄弟団の騎士ファルクとその従者ニコラ。ローレントの娘アミーナが語り手の役を担う。犯人は魔術を使って〈走狗〉と呼ばれる身代わりを使いローレントを殺させたらしい。〈走狗〉はその後自分のしたことを忘れてしまうので、下手人捜しは至難の業である。しかし、ファルクは決然と言う。「たとえ誰かが魔術師であったとしても、また誰がどのような魔術を用いたとしても、それでも〈走狗〉は彼である、または彼ではない、という理由を見つけ出すのだ」と。ここに本書が本格ミステリとして成立している根拠がある。本書においては、魔法と言っても、厳然として作られたルールに縛られており、それに則って論理的に考えていけば、事件の解決に至るのだ。決してルールからはみ出したり、ルール自体を疑うこともなく、作品は見事に完結する。面白いことは面白いのだが、まあ、よくできたパズルみたいなもので、それ以上の深みがあるわけではない。語り手であるアミーナを始め、探偵役のファルクとニコラ、どのキャラクターも平板で、ちょっと物足りない気がする。知的遊戯としては十分及第点なのだが……。
このミス上位にこのような作品が来るというのは少し驚きではある。綾辻行人ら新本格の登場のような衝撃はないけれど、こうして世代交代というのはゆるやかに進んでいくのかもしれない。
最近のコメント