小松左京その3(女シリーズ・芸道もの) ― 2012-03-05 00:00
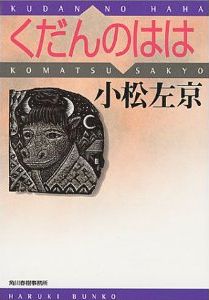
本年も昨年に引き続き、小松左京の旧作を読んでいく。実は女シリーズ・芸道ものは若い頃はほとんど読んでおらず、今回初めて読んでみた。結論から言えば、女シリーズは出来不出来の差が大きい。「ハイネックの女」「昔の女」などホラー系統の作品は残念ながらフォーミュラ・フィクションを脱しきれていない。「写真の女」のオチはあんまりだと思うし、「歌う女」はもう少しひねれば傑作になったかもと惜しまれる作品だ。芸道ものには、それほどハズレはない。ハルキ文庫版で『くだんのはは』と『高砂幻戯』の二冊を読めば、女シリーズは10編全てを、芸道ものは全12編のうち10編を読むことができる。全て読んでみて、傑作と思ったのは以下の三篇である。
「旅する女」(『高砂幻戯』所収)
四年前に失くしたあるものを探すために世界中を一人で旅する女、滝川夫人とタヒチのホテルで出会った「彼」は、二十年前の学生時代に付き合っていた水商売の女性を思い出す。滝川夫人は、ずっと彼が行方を探している彼女に似ていたのだ。どこが似ているのかと問う夫人に対して「彼」は答える。「私のとよく似ていながら、まったくちがった世界、すれちがうことはできても絶対に出あえないような世界を、一人で旅していらっしゃる所……」。求めても得られない何かを探しているという点で、夫人と「彼」は同一なのである。得られないとわかっていてもなお失われたものを求めざるを得ない人間の業の深さ、凄まじさ。これを本編の結末は見事にえぐり出し、読者に強烈な印象を残す幕切れとなっている。
「流れる女」(『くだんのはは』所収)
おそらく金沢がモデルと思われる古都K市を舞台に、還暦間近の主人公の恋と義父の恋、息子の恋、三世代にまたがる恋が同時に描かれる。三年前に妻を亡くした「私」は、どう見ても三十代にしか見えない五十すぎの女性、芸事の師匠をしている小出ゆきと知り合い、恋に落ちる。同じく妻を亡くした八十近くの義父と暮らす「私」は、どうやらゆきと義父が会っていることに気づく。そんなとき、息子の一郎が芸者と結婚したいと連絡をしてきた。「私」が実際に会うことになった息子の結婚相手とは……。詳細な情景描写から始まって、お茶道具、小唄端唄など芸事の具体的な叙述に至るまで、本編は見事なリアリズムに貫かれている。このリアリズムがあってこそ、あっと驚く非現実的な結末の衝撃が保証されているわけだ。女シリーズの白眉というべき傑作である。
「天神山縁糸苧環(てんじんやまえにしのおだまき)」(『高砂幻戯』所収)
上方落語の大物桂文都師匠(モデルは桂米朝)の弟子小文が真打ちに昇進することになり、その襲名披露興行で、師匠は封印していた大ネタ「立ち切れ」をやることになる。「立ち切れ」の中に出てくる芸者小糸と、若かりし文都を恋して非業の死を遂げた芸者小糸との人生とが絡み合い、もつれ合って、物語は文都演じる「立ち切れ」のクライマックスへと至る……。これ、ホントにいい話で、自分は結末付近でじわりと感動が湧き上がり、涙をこらえることができなかった。小松左京の作品で泣いたのは初めてかもしれない。山崎正和は文春文庫版『日本沈没』の解説で「この作者の本質は抒情詩人である」と鋭い指摘をしているが、本編などを読むとまさにその通りに思えてくる。
以上三篇、未読の方はぜひとも読んでみてほしい。小説的完成度を放棄したと思われがちな小松左京ではあるが、その気になれば十分完成された小説を書くことができたのだということがわかってもらえると思う。ただし、考慮すべき点は、「流れる女」はピランデルロのある戯曲を元にしており、「天神山縁糸苧環」は落語「立ち切れ」の変奏曲に他ならないという事実である。「鷺娘」という芸道ものの中で、ノルウェー人のハンスに「日本固有のものって何だ?」と尋ねられた作家大杉(無論モデルは小松自身)が「日本オリジナルなものより、世界中から流れこんだいろんなエレメントの、後世へかけての受け入れ方、発展のさせ方、変形のしかたに、日本固有のものがあるかもしれない」と語っているが、まさにそのオリジナルに対する「発展のさせ方、変形のしかた」の巧さに、小松左京の魅力の一つはあるのではないだろうか。
「旅する女」(『高砂幻戯』所収)
四年前に失くしたあるものを探すために世界中を一人で旅する女、滝川夫人とタヒチのホテルで出会った「彼」は、二十年前の学生時代に付き合っていた水商売の女性を思い出す。滝川夫人は、ずっと彼が行方を探している彼女に似ていたのだ。どこが似ているのかと問う夫人に対して「彼」は答える。「私のとよく似ていながら、まったくちがった世界、すれちがうことはできても絶対に出あえないような世界を、一人で旅していらっしゃる所……」。求めても得られない何かを探しているという点で、夫人と「彼」は同一なのである。得られないとわかっていてもなお失われたものを求めざるを得ない人間の業の深さ、凄まじさ。これを本編の結末は見事にえぐり出し、読者に強烈な印象を残す幕切れとなっている。
「流れる女」(『くだんのはは』所収)
おそらく金沢がモデルと思われる古都K市を舞台に、還暦間近の主人公の恋と義父の恋、息子の恋、三世代にまたがる恋が同時に描かれる。三年前に妻を亡くした「私」は、どう見ても三十代にしか見えない五十すぎの女性、芸事の師匠をしている小出ゆきと知り合い、恋に落ちる。同じく妻を亡くした八十近くの義父と暮らす「私」は、どうやらゆきと義父が会っていることに気づく。そんなとき、息子の一郎が芸者と結婚したいと連絡をしてきた。「私」が実際に会うことになった息子の結婚相手とは……。詳細な情景描写から始まって、お茶道具、小唄端唄など芸事の具体的な叙述に至るまで、本編は見事なリアリズムに貫かれている。このリアリズムがあってこそ、あっと驚く非現実的な結末の衝撃が保証されているわけだ。女シリーズの白眉というべき傑作である。
「天神山縁糸苧環(てんじんやまえにしのおだまき)」(『高砂幻戯』所収)
上方落語の大物桂文都師匠(モデルは桂米朝)の弟子小文が真打ちに昇進することになり、その襲名披露興行で、師匠は封印していた大ネタ「立ち切れ」をやることになる。「立ち切れ」の中に出てくる芸者小糸と、若かりし文都を恋して非業の死を遂げた芸者小糸との人生とが絡み合い、もつれ合って、物語は文都演じる「立ち切れ」のクライマックスへと至る……。これ、ホントにいい話で、自分は結末付近でじわりと感動が湧き上がり、涙をこらえることができなかった。小松左京の作品で泣いたのは初めてかもしれない。山崎正和は文春文庫版『日本沈没』の解説で「この作者の本質は抒情詩人である」と鋭い指摘をしているが、本編などを読むとまさにその通りに思えてくる。
以上三篇、未読の方はぜひとも読んでみてほしい。小説的完成度を放棄したと思われがちな小松左京ではあるが、その気になれば十分完成された小説を書くことができたのだということがわかってもらえると思う。ただし、考慮すべき点は、「流れる女」はピランデルロのある戯曲を元にしており、「天神山縁糸苧環」は落語「立ち切れ」の変奏曲に他ならないという事実である。「鷺娘」という芸道ものの中で、ノルウェー人のハンスに「日本固有のものって何だ?」と尋ねられた作家大杉(無論モデルは小松自身)が「日本オリジナルなものより、世界中から流れこんだいろんなエレメントの、後世へかけての受け入れ方、発展のさせ方、変形のしかたに、日本固有のものがあるかもしれない」と語っているが、まさにそのオリジナルに対する「発展のさせ方、変形のしかた」の巧さに、小松左京の魅力の一つはあるのではないだろうか。
最近のコメント