イアン・マクドナルド『旋舞の千年都市』 ― 2014-05-25 22:28

本書は、近未来のイスタンブールを舞台に、心臓病のため聴覚を遮断されている子どもジャン、テロを間近で目撃して以来精霊(ジン)が見えるようになった青年ネジュデット、かつては反政府運動の闘士として活動した過去を持つ元大学教授ゲオルギオス、画廊を営む美術商の女性アイシェと遣り手のトレーダーである青年アドナンのカップルなど、様々な地位と年齢の人々の、月曜日から金曜日、即ちわずか5日間の出来事を描いた物語である。
ストーリイの主軸は二つ。一方はテロに巻き込まれていく子どもジャンと青年ネジュデットの物語、もう一方はイスタンブールに存在したと言われる伝説の「蜜人」を巡るアイシェたちの物語だ。前者は、ジャンが作った群遊ロボットのカメラアイを通じて空間を超え、後者は「蜜人」を追い求める過程で東洋と西洋を結ぶ古都イスタンブールの歴史を浮かび上がらせる。横軸と縦軸、空間と時間の広がりを背景に、ナノテクノロジー、行動経済学、群遊ロボットなど数多くのアイディア、ガジェットが詰め込まれ、現在形の動詞を主とした短文を積み重ねたリズム感溢れる魅力的な文体(これは翻訳の力が大きい)で語られている。
マクドナルドの作家的な立ち位置は、西洋の近代合理主義をケルトやインドやトルコといった、非西洋の立場から見つめ直し、問い直そうというものだと理解している。単純に土俗的なものの勝利で終わるのではなく、西洋と非西洋が入り混じり、土俗とテクノロジーが融合していく、その混淆をこそマクドナルドは好んで描く。そうした意味で、本書の舞台がイスタンブールとなるのは、必然でもあった。
最初のうちは登場人物も多くエピソードがばらばらで、すぐに場面転換してしまうので、読み進めるのが辛いけれど、それを乗り越えてしまえば(木曜日あたりから)、読者はぐいぐいと物語に突き動かされ、感動の結末へと辿り着く。『サイバラバード・デイズ』のように人間性を超えた彼岸を目指したのではなく、あくまでも男女を巡る人間的な、あまりに人間的な結末に少々不満は残るが、これだけ楽しませてくれたのだから、文句は言うまい。後は、イスタンブールの熱気が直に伝わってくるかのような緻密な描写に随分と酔わされた。筆者は十数年前にイスタンブールを一度訪れたことがあるが、本書を読みながら、その時の街の様子、朝の空気がまざまざと蘇ってきたのには驚いた。マクドナルドの描写力というか文章力は、かなりのものだと思う。さらに、詳細が書けないのが残念であるが、筆者も幼少時に観ていた某海外アニメが最後に重要な役割を果たしているのも、個人的にはうれしい驚きであった。何はともあれ、創元海外SF叢書第一弾にふさわしい、必読の力作である。
ストーリイの主軸は二つ。一方はテロに巻き込まれていく子どもジャンと青年ネジュデットの物語、もう一方はイスタンブールに存在したと言われる伝説の「蜜人」を巡るアイシェたちの物語だ。前者は、ジャンが作った群遊ロボットのカメラアイを通じて空間を超え、後者は「蜜人」を追い求める過程で東洋と西洋を結ぶ古都イスタンブールの歴史を浮かび上がらせる。横軸と縦軸、空間と時間の広がりを背景に、ナノテクノロジー、行動経済学、群遊ロボットなど数多くのアイディア、ガジェットが詰め込まれ、現在形の動詞を主とした短文を積み重ねたリズム感溢れる魅力的な文体(これは翻訳の力が大きい)で語られている。
マクドナルドの作家的な立ち位置は、西洋の近代合理主義をケルトやインドやトルコといった、非西洋の立場から見つめ直し、問い直そうというものだと理解している。単純に土俗的なものの勝利で終わるのではなく、西洋と非西洋が入り混じり、土俗とテクノロジーが融合していく、その混淆をこそマクドナルドは好んで描く。そうした意味で、本書の舞台がイスタンブールとなるのは、必然でもあった。
最初のうちは登場人物も多くエピソードがばらばらで、すぐに場面転換してしまうので、読み進めるのが辛いけれど、それを乗り越えてしまえば(木曜日あたりから)、読者はぐいぐいと物語に突き動かされ、感動の結末へと辿り着く。『サイバラバード・デイズ』のように人間性を超えた彼岸を目指したのではなく、あくまでも男女を巡る人間的な、あまりに人間的な結末に少々不満は残るが、これだけ楽しませてくれたのだから、文句は言うまい。後は、イスタンブールの熱気が直に伝わってくるかのような緻密な描写に随分と酔わされた。筆者は十数年前にイスタンブールを一度訪れたことがあるが、本書を読みながら、その時の街の様子、朝の空気がまざまざと蘇ってきたのには驚いた。マクドナルドの描写力というか文章力は、かなりのものだと思う。さらに、詳細が書けないのが残念であるが、筆者も幼少時に観ていた某海外アニメが最後に重要な役割を果たしているのも、個人的にはうれしい驚きであった。何はともあれ、創元海外SF叢書第一弾にふさわしい、必読の力作である。
鈴木創『なごや古本屋案内』 ― 2014-04-29 06:45

ちょっと古いが、2013年11月に地元名古屋の風媒社から発行された本。中学1年のときから鶴舞・上前津といった名古屋の古書街に足繁く通い、高校生のときには自らの進路を語る3分間スピーチで「古本屋になりたい」と言い切った筆者にとって、本書は見逃せない一冊だ。
「なごや」と言いながら実際には愛知・岐阜・三重を幅広くカバーしているため、本書に登場する古本屋をすべて知っているわけではない。また、自分に興味のある分野は限られているため、実際に本書を見てこの古本屋へ行こうということはあまりないだろう。それでも、本書が読んでいて面白いのは、店主のインタビューを中心としているために、店主の本に対する思い、古本屋への思いが直に伝わってくるところである。多くの同種のガイドブックは、当たり前だが、そこがどんな本屋でどんな本を扱っているかということを中心としている。というか、それしかない場合がほとんどであろう。編著者の鈴木さんは自ら「シマウマ書房」という古本屋の店主であり、他の店主への敬意を払ってインタビューに臨んでいることが文章からもよくわかる。そうか、あの店にはこんな経緯があったのかとか、おお、あの人がこんなところで店を開いているとか、この辺りの古本屋をよく知る者にとっては驚きに満ちているし、そうでない人にとっても、古本屋というものを理解する一助となるはずだ。清水良典、諏訪哲史といった地元在住の評論家、作家が古本屋に関するエッセイを寄稿しているのも読んでいて楽しい企画となっている。SFファンにとっては、地元のBNF岡田正哉氏が30年前の名古屋の古本屋を紹介するエッセイが読めるのがうれしい贈り物だ(高井信さん、ありがとうございます)。
中学生の頃、なけなしのお金をはたいてCOMを買った山星書店。つたや書店では、SFマガジンのバックナンバーを大量に買い込み、自転車の荷台にくくりつけて帰った。ブラックユーモア全集を揃いで買った大学堂。煙草の匂いがしみついたハヤカワ文庫の中からちょっとでもいいものを選んで買った千代田書店。春日井で営業していた椙山書店が店を閉める時には、本棚をたくさん貰って帰った(今目の前にあるのがそれだ)。海星堂に、自分が作った同人誌が売っていた時にはびっくりしたなあ。シマウマ書房で綺麗なアメージングストーリーズ日本語版を一挙に6冊購入した時は手が震えたよ。想い出を書き出せばきりがない。本書を読むことは、自分にとって人生を振り返る旅でもあった。
「なごや」と言いながら実際には愛知・岐阜・三重を幅広くカバーしているため、本書に登場する古本屋をすべて知っているわけではない。また、自分に興味のある分野は限られているため、実際に本書を見てこの古本屋へ行こうということはあまりないだろう。それでも、本書が読んでいて面白いのは、店主のインタビューを中心としているために、店主の本に対する思い、古本屋への思いが直に伝わってくるところである。多くの同種のガイドブックは、当たり前だが、そこがどんな本屋でどんな本を扱っているかということを中心としている。というか、それしかない場合がほとんどであろう。編著者の鈴木さんは自ら「シマウマ書房」という古本屋の店主であり、他の店主への敬意を払ってインタビューに臨んでいることが文章からもよくわかる。そうか、あの店にはこんな経緯があったのかとか、おお、あの人がこんなところで店を開いているとか、この辺りの古本屋をよく知る者にとっては驚きに満ちているし、そうでない人にとっても、古本屋というものを理解する一助となるはずだ。清水良典、諏訪哲史といった地元在住の評論家、作家が古本屋に関するエッセイを寄稿しているのも読んでいて楽しい企画となっている。SFファンにとっては、地元のBNF岡田正哉氏が30年前の名古屋の古本屋を紹介するエッセイが読めるのがうれしい贈り物だ(高井信さん、ありがとうございます)。
中学生の頃、なけなしのお金をはたいてCOMを買った山星書店。つたや書店では、SFマガジンのバックナンバーを大量に買い込み、自転車の荷台にくくりつけて帰った。ブラックユーモア全集を揃いで買った大学堂。煙草の匂いがしみついたハヤカワ文庫の中からちょっとでもいいものを選んで買った千代田書店。春日井で営業していた椙山書店が店を閉める時には、本棚をたくさん貰って帰った(今目の前にあるのがそれだ)。海星堂に、自分が作った同人誌が売っていた時にはびっくりしたなあ。シマウマ書房で綺麗なアメージングストーリーズ日本語版を一挙に6冊購入した時は手が震えたよ。想い出を書き出せばきりがない。本書を読むことは、自分にとって人生を振り返る旅でもあった。
関根康人『土星の衛星タイタンに生命体がいる!』 ― 2014-04-27 13:21

2010年6月に小惑星探査を終えて地球に帰還した探査機「はやぶさ」のニュースは記憶に新しいと思う。「はやぶさ」が小惑星イトカワに着陸したのは、帰還から5年遡った2005年5月のこと。実はその半年ほど前、2004年12月にNASAのカッシーニ探査機が土星系に到着していたのだが、このことを覚えている人はどのくらいいるだろうか。筆者にとって衝撃的だったのは、着陸機ホイヘンス(こちらは欧州宇宙機関ESAが開発した)が送ってきた土星の衛星タイタン地表の画像だった。何とそこには地球とよく似た川や海が映っていたのである。しかも、ホイヘンスが着陸した地点は、石がごろごろ転がる地球の河原に酷似していた(写真参照)。むろん、太陽から14億キロ以上離れ、最高気温がマイナス100度Cのタイタンに液体の水は存在しない。これはメタンの海や河川であり、メタンが地表を浸食した結果の地形である。タイタンに大気があることは知っていたのだが、まさかこんなにも地球とよく似た地形になっているとは思わなかった。当時ものすごく興奮し、日本で報道の扱いが小さいのに憤った記憶がある。
さて、本書(2013年12月発行、小学館新書)は、そのタイタンがなぜこんなに地球とよく似た地形になったかの謎を解き明かしてくれるだけでなく、太陽系内の他の惑星や衛星の成り立ちから始まって、惑星探査の歴史を辿り、それぞれの惑星や衛星における生命体存在の可能性を探った、良質の惑星科学解説書となっている。特に印象的なのは、2章で紹介される2種類の「ハビタブルゾーン」という概念だ。地球に存在するような生命が生きていく環境には、太陽光の日射エネルギーによって惑星表面に液体が存在する太陽加熱型ハビタブルゾーンと、潮汐による摩擦エネルギーで液体が内部に存在する潮汐加熱型ハビタブルゾーンとがある。分厚い氷の下に液体の水を持つ木星の衛星エウロパや、内部の海水を激しく噴出している土星の衛星エンセラダスは、典型的な「潮汐加熱型ハビタブルゾーン」であり、メタンの海を地表に持つタイタンは、地球以外に唯一存在する「太陽加熱型ハビタブルゾーン」だということになるわけだ。地球上の生命が、光合成でできた酸素と有機物を燃やして再び水と二酸化炭素に戻す過程で太陽光エネルギーを取り出しているように、タイタンの生命体は、アセチレンと水素を使ってメタンを作り出す過程で太陽光エネルギーを利用しているのではないか、と科学者達は推測している。カッシーニの観測結果もその説に沿ったものであるが、生命以外のプロセスで結果が生じている可能性もあるので、今後の探査を待つしかないというのが本書の結論である。従って、題名の「いる!」は「いる!?」が妥当であろう。
それにしても、本書で想像されている、大気中を飛び回るタイタンの生命体の姿は実に面白い。これはもはやSFの面白さとほとんど同じである。実際、本書の中では、エウロパの生命体を考察する際に、クラーク『2010年宇宙の旅』の一場面が挿入されたり、タイタンの地表を、ヴォネガット『タイタンの妖女』における描写と比較したり(これがまたぴったり一致しているのだ!)、自然にSFと科学解説が入り混じっていて、その自由闊達さも本書の魅力の一つとなっている。SFファンにはぜひ一読をお薦めしたいし、そうでない人にも十分楽しめる、初心者向けの良書である。
さて、本書(2013年12月発行、小学館新書)は、そのタイタンがなぜこんなに地球とよく似た地形になったかの謎を解き明かしてくれるだけでなく、太陽系内の他の惑星や衛星の成り立ちから始まって、惑星探査の歴史を辿り、それぞれの惑星や衛星における生命体存在の可能性を探った、良質の惑星科学解説書となっている。特に印象的なのは、2章で紹介される2種類の「ハビタブルゾーン」という概念だ。地球に存在するような生命が生きていく環境には、太陽光の日射エネルギーによって惑星表面に液体が存在する太陽加熱型ハビタブルゾーンと、潮汐による摩擦エネルギーで液体が内部に存在する潮汐加熱型ハビタブルゾーンとがある。分厚い氷の下に液体の水を持つ木星の衛星エウロパや、内部の海水を激しく噴出している土星の衛星エンセラダスは、典型的な「潮汐加熱型ハビタブルゾーン」であり、メタンの海を地表に持つタイタンは、地球以外に唯一存在する「太陽加熱型ハビタブルゾーン」だということになるわけだ。地球上の生命が、光合成でできた酸素と有機物を燃やして再び水と二酸化炭素に戻す過程で太陽光エネルギーを取り出しているように、タイタンの生命体は、アセチレンと水素を使ってメタンを作り出す過程で太陽光エネルギーを利用しているのではないか、と科学者達は推測している。カッシーニの観測結果もその説に沿ったものであるが、生命以外のプロセスで結果が生じている可能性もあるので、今後の探査を待つしかないというのが本書の結論である。従って、題名の「いる!」は「いる!?」が妥当であろう。
それにしても、本書で想像されている、大気中を飛び回るタイタンの生命体の姿は実に面白い。これはもはやSFの面白さとほとんど同じである。実際、本書の中では、エウロパの生命体を考察する際に、クラーク『2010年宇宙の旅』の一場面が挿入されたり、タイタンの地表を、ヴォネガット『タイタンの妖女』における描写と比較したり(これがまたぴったり一致しているのだ!)、自然にSFと科学解説が入り混じっていて、その自由闊達さも本書の魅力の一つとなっている。SFファンにはぜひ一読をお薦めしたいし、そうでない人にも十分楽しめる、初心者向けの良書である。
ジーン・ウルフ『ピース』 ― 2014-04-13 11:20
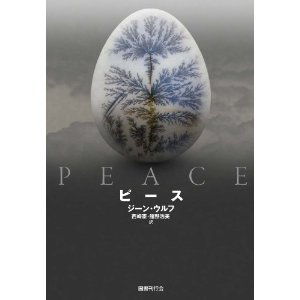
ブログさぼっていてすみません。8か月ぶりですが、ようやく1月刊行のウルフが読めたので、レビューを再開します。
SF、ファンタジイ界きっての超絶技巧派作家ウルフの初期長編(1975年刊行)が四十年程の時を経て遂に訳された。刊行当初から海外SFファンの間で話題になっていた『ケルベロス第五の首』とは違い、アメリカ中西部の架空の街を舞台にして、一人の男の生涯を少年時代、壮年時代、晩年が複雑に絡み合った構成で描いた、一風変わった幻想文学とでも呼ぶべき本書は、さほどSF界では話題になっておらず、正直どんな感じの作品なのか不安を抱きながら読み始めた。
いや、結論から言うと、そんな心配は無用であった。記憶と書物、書かれたことと現実との相互作用という一貫した主題のもとに、緻密に計算された物語と、一見無関係に語られる様々な挿話が二重三重の塊となって読者の想像力を直撃する。いつものウルフがここにはあった。SFだろうが、ファンタジイだろうが、現代文学だろうが、ジャンルはもはや関係なく、この語り口こそがウルフなのだ。そう言い切りたくなるほどの個性的な語り方がここにはある。本書を読むことは、言ってみれば、濃密な霧の中をゆっくり一歩ずつ歩んでいるうちに霧が晴れて、辺りの景色がぼんやりと見えてくるかのような体験だ。完全に霧が晴れることはない。景色が曖昧なまま、物語は終わる。後は読者が想像するしかない。主人公オールデン・デニス・ウィアとは何者だったのか。彼は五歳のときにボビー・ブラックに何をしたのか。大人になってどうやって大金を得たのか。ロイス・アーバスノットとの間に何があったのか。すべては曖昧なまま残される。その反面、少年時代に過ごした館の様子、預けられた叔母と婚約者との想い出など、細部は異様に細かく、微に入り細に渡って丁寧に描写されている。つまり霧の中から垣間見える部分部分ははっきりしているのに、そこから得られるはずの全体像は曖昧なままなのだ。謎が解けそうなんだけれど、後一歩で解けない。このもどかしさこそが実はウルフを読む楽しみでもある。その昔(もう27年も前だ)、筆者はウルフの『拷問者の影』を読んだときにこう書評したことがある。「我々読者は物語を読むときに終わりを求めているのであり、その終わりへの欲望を、物語は常に少しずつ先へ延ばそうとする。終わろうとする欲望と終わらせまいとする欲望とが一体となって物語の終わりへと突き進むところにこそ物語の快感はあるのだ」と。この気持ちは、本書を読み終えた今も少しも変わらない。すべての謎を解きたい我々読者とすべてを語ろうとはしないウルフとの駆け引きこそが本書を読む楽しさである。さあ、存分に楽しもうではないか。何度も、何度でも。
SF、ファンタジイ界きっての超絶技巧派作家ウルフの初期長編(1975年刊行)が四十年程の時を経て遂に訳された。刊行当初から海外SFファンの間で話題になっていた『ケルベロス第五の首』とは違い、アメリカ中西部の架空の街を舞台にして、一人の男の生涯を少年時代、壮年時代、晩年が複雑に絡み合った構成で描いた、一風変わった幻想文学とでも呼ぶべき本書は、さほどSF界では話題になっておらず、正直どんな感じの作品なのか不安を抱きながら読み始めた。
いや、結論から言うと、そんな心配は無用であった。記憶と書物、書かれたことと現実との相互作用という一貫した主題のもとに、緻密に計算された物語と、一見無関係に語られる様々な挿話が二重三重の塊となって読者の想像力を直撃する。いつものウルフがここにはあった。SFだろうが、ファンタジイだろうが、現代文学だろうが、ジャンルはもはや関係なく、この語り口こそがウルフなのだ。そう言い切りたくなるほどの個性的な語り方がここにはある。本書を読むことは、言ってみれば、濃密な霧の中をゆっくり一歩ずつ歩んでいるうちに霧が晴れて、辺りの景色がぼんやりと見えてくるかのような体験だ。完全に霧が晴れることはない。景色が曖昧なまま、物語は終わる。後は読者が想像するしかない。主人公オールデン・デニス・ウィアとは何者だったのか。彼は五歳のときにボビー・ブラックに何をしたのか。大人になってどうやって大金を得たのか。ロイス・アーバスノットとの間に何があったのか。すべては曖昧なまま残される。その反面、少年時代に過ごした館の様子、預けられた叔母と婚約者との想い出など、細部は異様に細かく、微に入り細に渡って丁寧に描写されている。つまり霧の中から垣間見える部分部分ははっきりしているのに、そこから得られるはずの全体像は曖昧なままなのだ。謎が解けそうなんだけれど、後一歩で解けない。このもどかしさこそが実はウルフを読む楽しみでもある。その昔(もう27年も前だ)、筆者はウルフの『拷問者の影』を読んだときにこう書評したことがある。「我々読者は物語を読むときに終わりを求めているのであり、その終わりへの欲望を、物語は常に少しずつ先へ延ばそうとする。終わろうとする欲望と終わらせまいとする欲望とが一体となって物語の終わりへと突き進むところにこそ物語の快感はあるのだ」と。この気持ちは、本書を読み終えた今も少しも変わらない。すべての謎を解きたい我々読者とすべてを語ろうとはしないウルフとの駆け引きこそが本書を読む楽しさである。さあ、存分に楽しもうではないか。何度も、何度でも。
チャイナ・ミエヴィル『クラーケン』 ― 2013-08-14 22:29

『言語都市』が傑作だったので、期待して読み始めたのだが、ロンドン自然史博物館からダイオウイカが水槽ごと消え、博物館のキュレーターをしている男の友人レオンが、突然小包から現れた謎の二人組ゴスとサビーに襲われ、食われてしまう場面まで読んではたと気づいた。これ、『言語都市』とは全く系統が違うぞと(遅いか)。本書はロンドンの裏側に脈々と流れる裏の歴史を描いた一種のダーク・ファンタジイなのである。その意味では、ロンドンの地下での戦いを描いたデビュー作『キング・ラット』に似た作品だと言える。
イカの行方を知っているはずだと誤解された主人公のキュレーター、ビリーはスキンヘッドの筋骨たくましい男デインと逃げることになり、これに「原理主義者およびセクト関連犯罪捜査班」の警部、巡査や、ロンドンに存在する数多くのセクト〈ロンドンマンサー〉〈ガンファーマーズ〉〈カオス・ナチス〉などなどが絡んで、ダイオウイカそっちのけで延々と続く追っかけが始まるわけだ。主にキャラクターで読ませる小説であり、アメコミを小説にしたような雰囲気がある。とりわけ、悪の君主タトゥーの設定(人間の背中にとり憑く刺青)は、非常に漫画的またはアニメ的だ。数多くの地口、カルトや宗教に関する蘊蓄(うんちく)、実在の建物や地名、ドラマネタ(本書で初めて『時空刑事1973ライフ・オン・マーズ』なんてのを知ったぞ)をぶち込んで語られる追っかけ、また追っかけ、アクションまたアクション。作者がとても楽しんで語っているのはわかるのだが、これはちょっと詰め込まれたネタが過剰過ぎるのではなかろうか。出てくる音楽もイット・バイツにゲイリー・グリッター、ソルトンペパーにカニエ・ウエスト、エイミー・ワインハウスでは本当に無茶苦茶で(それがねらいだとしても)、単に出してみましたといった感じにしか見えない。スード・エコーの「ファンキー・タウン」とスペシャルズの「ゴースト・タウン」はロンドンを象徴してるととれなくもないのでいいなとは思ったが。ともかく、全体的にもうちょっと刈り込んで、コンパクトにまとめた方がよかったのではという気がした。
最後に音楽の訳語だが、プリンスの『キス』は『キッス』の方が、Run-D.M.C.はRUN-DMCまたはRUN DMCの方が馴染んでいると思う。
イカの行方を知っているはずだと誤解された主人公のキュレーター、ビリーはスキンヘッドの筋骨たくましい男デインと逃げることになり、これに「原理主義者およびセクト関連犯罪捜査班」の警部、巡査や、ロンドンに存在する数多くのセクト〈ロンドンマンサー〉〈ガンファーマーズ〉〈カオス・ナチス〉などなどが絡んで、ダイオウイカそっちのけで延々と続く追っかけが始まるわけだ。主にキャラクターで読ませる小説であり、アメコミを小説にしたような雰囲気がある。とりわけ、悪の君主タトゥーの設定(人間の背中にとり憑く刺青)は、非常に漫画的またはアニメ的だ。数多くの地口、カルトや宗教に関する蘊蓄(うんちく)、実在の建物や地名、ドラマネタ(本書で初めて『時空刑事1973ライフ・オン・マーズ』なんてのを知ったぞ)をぶち込んで語られる追っかけ、また追っかけ、アクションまたアクション。作者がとても楽しんで語っているのはわかるのだが、これはちょっと詰め込まれたネタが過剰過ぎるのではなかろうか。出てくる音楽もイット・バイツにゲイリー・グリッター、ソルトンペパーにカニエ・ウエスト、エイミー・ワインハウスでは本当に無茶苦茶で(それがねらいだとしても)、単に出してみましたといった感じにしか見えない。スード・エコーの「ファンキー・タウン」とスペシャルズの「ゴースト・タウン」はロンドンを象徴してるととれなくもないのでいいなとは思ったが。ともかく、全体的にもうちょっと刈り込んで、コンパクトにまとめた方がよかったのではという気がした。
最後に音楽の訳語だが、プリンスの『キス』は『キッス』の方が、Run-D.M.C.はRUN-DMCまたはRUN DMCの方が馴染んでいると思う。
最近のコメント