ジーン・ウルフ『ピース』 ― 2014-04-13 11:20
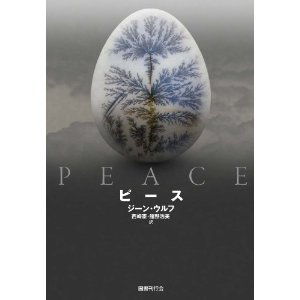
ブログさぼっていてすみません。8か月ぶりですが、ようやく1月刊行のウルフが読めたので、レビューを再開します。
SF、ファンタジイ界きっての超絶技巧派作家ウルフの初期長編(1975年刊行)が四十年程の時を経て遂に訳された。刊行当初から海外SFファンの間で話題になっていた『ケルベロス第五の首』とは違い、アメリカ中西部の架空の街を舞台にして、一人の男の生涯を少年時代、壮年時代、晩年が複雑に絡み合った構成で描いた、一風変わった幻想文学とでも呼ぶべき本書は、さほどSF界では話題になっておらず、正直どんな感じの作品なのか不安を抱きながら読み始めた。
いや、結論から言うと、そんな心配は無用であった。記憶と書物、書かれたことと現実との相互作用という一貫した主題のもとに、緻密に計算された物語と、一見無関係に語られる様々な挿話が二重三重の塊となって読者の想像力を直撃する。いつものウルフがここにはあった。SFだろうが、ファンタジイだろうが、現代文学だろうが、ジャンルはもはや関係なく、この語り口こそがウルフなのだ。そう言い切りたくなるほどの個性的な語り方がここにはある。本書を読むことは、言ってみれば、濃密な霧の中をゆっくり一歩ずつ歩んでいるうちに霧が晴れて、辺りの景色がぼんやりと見えてくるかのような体験だ。完全に霧が晴れることはない。景色が曖昧なまま、物語は終わる。後は読者が想像するしかない。主人公オールデン・デニス・ウィアとは何者だったのか。彼は五歳のときにボビー・ブラックに何をしたのか。大人になってどうやって大金を得たのか。ロイス・アーバスノットとの間に何があったのか。すべては曖昧なまま残される。その反面、少年時代に過ごした館の様子、預けられた叔母と婚約者との想い出など、細部は異様に細かく、微に入り細に渡って丁寧に描写されている。つまり霧の中から垣間見える部分部分ははっきりしているのに、そこから得られるはずの全体像は曖昧なままなのだ。謎が解けそうなんだけれど、後一歩で解けない。このもどかしさこそが実はウルフを読む楽しみでもある。その昔(もう27年も前だ)、筆者はウルフの『拷問者の影』を読んだときにこう書評したことがある。「我々読者は物語を読むときに終わりを求めているのであり、その終わりへの欲望を、物語は常に少しずつ先へ延ばそうとする。終わろうとする欲望と終わらせまいとする欲望とが一体となって物語の終わりへと突き進むところにこそ物語の快感はあるのだ」と。この気持ちは、本書を読み終えた今も少しも変わらない。すべての謎を解きたい我々読者とすべてを語ろうとはしないウルフとの駆け引きこそが本書を読む楽しさである。さあ、存分に楽しもうではないか。何度も、何度でも。
SF、ファンタジイ界きっての超絶技巧派作家ウルフの初期長編(1975年刊行)が四十年程の時を経て遂に訳された。刊行当初から海外SFファンの間で話題になっていた『ケルベロス第五の首』とは違い、アメリカ中西部の架空の街を舞台にして、一人の男の生涯を少年時代、壮年時代、晩年が複雑に絡み合った構成で描いた、一風変わった幻想文学とでも呼ぶべき本書は、さほどSF界では話題になっておらず、正直どんな感じの作品なのか不安を抱きながら読み始めた。
いや、結論から言うと、そんな心配は無用であった。記憶と書物、書かれたことと現実との相互作用という一貫した主題のもとに、緻密に計算された物語と、一見無関係に語られる様々な挿話が二重三重の塊となって読者の想像力を直撃する。いつものウルフがここにはあった。SFだろうが、ファンタジイだろうが、現代文学だろうが、ジャンルはもはや関係なく、この語り口こそがウルフなのだ。そう言い切りたくなるほどの個性的な語り方がここにはある。本書を読むことは、言ってみれば、濃密な霧の中をゆっくり一歩ずつ歩んでいるうちに霧が晴れて、辺りの景色がぼんやりと見えてくるかのような体験だ。完全に霧が晴れることはない。景色が曖昧なまま、物語は終わる。後は読者が想像するしかない。主人公オールデン・デニス・ウィアとは何者だったのか。彼は五歳のときにボビー・ブラックに何をしたのか。大人になってどうやって大金を得たのか。ロイス・アーバスノットとの間に何があったのか。すべては曖昧なまま残される。その反面、少年時代に過ごした館の様子、預けられた叔母と婚約者との想い出など、細部は異様に細かく、微に入り細に渡って丁寧に描写されている。つまり霧の中から垣間見える部分部分ははっきりしているのに、そこから得られるはずの全体像は曖昧なままなのだ。謎が解けそうなんだけれど、後一歩で解けない。このもどかしさこそが実はウルフを読む楽しみでもある。その昔(もう27年も前だ)、筆者はウルフの『拷問者の影』を読んだときにこう書評したことがある。「我々読者は物語を読むときに終わりを求めているのであり、その終わりへの欲望を、物語は常に少しずつ先へ延ばそうとする。終わろうとする欲望と終わらせまいとする欲望とが一体となって物語の終わりへと突き進むところにこそ物語の快感はあるのだ」と。この気持ちは、本書を読み終えた今も少しも変わらない。すべての謎を解きたい我々読者とすべてを語ろうとはしないウルフとの駆け引きこそが本書を読む楽しさである。さあ、存分に楽しもうではないか。何度も、何度でも。
コメント
トラックバック
このエントリのトラックバックURL: http://sciencefiction.asablo.jp/blog/2014/04/13/7273830/tb
_ 天竺堂の本棚 - 2014-06-27 14:20
ジーン・ウルフの初期の長編小説。
アメリカの田舎町に住んでる男性の回想らしいけど、何ともあやふやで幻想的。小説内の“現在”がよく分からないし、主人公が生きてるのか死んで ...
アメリカの田舎町に住んでる男性の回想らしいけど、何ともあやふやで幻想的。小説内の“現在”がよく分からないし、主人公が生きてるのか死んで ...
_ 天竺堂の本棚 - 2014-06-27 14:21
ジーン・ウルフの初期の長編小説。
アメリカの田舎町に住んでる男性の回想らしいけど、何ともあやふやで幻想的。小説内の“現在”がよく分からないし、主人公が生きてるのか死んで ...
アメリカの田舎町に住んでる男性の回想らしいけど、何ともあやふやで幻想的。小説内の“現在”がよく分からないし、主人公が生きてるのか死んで ...
最近のコメント