チャイナ・ミエヴィル『言語都市』 ― 2013-05-12 17:23

2月刊行の本だが、年度末から年度初めはいろいろ忙しく、じっくりと読みたい本でもあったので、5月の今まで取っておいた次第。3日程かけて一気に読み終えたが、いやこれは期待に違わぬ傑作であった。『都市と都市』よりもずっとこちらの好みに合う。間違いなく、本年度ベスト1候補である。
人類が宇宙に進出した遠い未来、ブレーメンという統治圏内の辺境惑星アリエカでは、原住民(アリエカ人)の都市の一角にエンバシータウンが建設され、交流と交易を行っていた。原住民はホストと呼ばれ、独特のゲンゴを操る。二つの口から同時に出る音で彼らは会話をする。だからと言って、二人の人間がただ同時に発声しただけでは、ホストと会話することはできない。二人の背後に一貫した思考や共感がなければ、ゲンゴにはならないのだ。かくしてクローン生成されたペアである「大使」が生み出され、ホストたちとコンタクトを取るようになった。また、ゲンゴには仮定や比喩が存在せず、事実しか述べることはできない。従って、比喩を述べたい場合、その比喩を表す人間を設定し、その人間(「直喩」と呼ばれる)を目の前にして語ることになる。要するに、「彼女の瞳はまるでダイヤのようだ」と言いたいときには、目の前に「ダイヤの瞳を持つ女」を表す「直喩」がいないとダメなわけだ。
この突拍子もないゲンゴの設定だけで、もうぞくぞくするよね。『バベル-17』にしろ『神狩り』にしろ、人間とは異なる超越的概念を描く際に言語からアプローチする手法というのは、そもそもサピア=ウォーフの仮設(言語こそが話者の世界観を形成し概念を作るものである)を基にしている。この仮説を逆手に取れば、たとえ理解できないと思われる存在であっても、言語の規則が理解できれば彼らの考えていることがわかるということになる。これがサイエンス・フィクションの方法と親和性が高いことは言うまでもない。有効性がかなり薄れた現在においてもなお、この仮説の魅力は薄れていないようで、本書は、その良い実践例となっている。
さて、主人公はエンバシータウンで生まれ育ったアヴィスという女性。彼女は、あちこちの都市を渡り歩きながら通常宇宙(マンヒマル)の背後に存在する恒常宇宙(イマー)に潜るイマーサーという仕事に就いていたが、ペルシアスという都市で異星言語学者サイルと出会ったことがきっかけとなり、故郷エンバシータウンに帰ることになる。そこで体験した様々な事件が、自身の生い立ちを交えて、彼女の口から落ち着いた口調で語られていく。クローン生成ではない赤の他人二人による大使エズ/ラーの赴任が引き起こしたアリエカ人への意外な反応、さらにはそれが惑星を揺るがす一大事件に発展していくとは誰も気づかなかった……。
落ち着いた語り口とは裏腹に次々と衝撃的な展開が待ち受けており、決して読者を飽きさせることはない。解決にやや安易さが見えることと、「直喩」の描き方が、ネイティヴ・アメリカンの名付け方の域を出ていないことなど不満はいくつかあるが、それでもこれだけ楽しませてくれたのだから文句はない。かつて『闇の左手』において文化人類学的手法をSFに融合させたル・グウィン本人が本書を絶賛しているのも当然だろう。もう一冊『クラーケン』が今年中に出るとのことで、チャイナ・ミエヴィルの快進撃はまだまだ続きそうだ。
人類が宇宙に進出した遠い未来、ブレーメンという統治圏内の辺境惑星アリエカでは、原住民(アリエカ人)の都市の一角にエンバシータウンが建設され、交流と交易を行っていた。原住民はホストと呼ばれ、独特のゲンゴを操る。二つの口から同時に出る音で彼らは会話をする。だからと言って、二人の人間がただ同時に発声しただけでは、ホストと会話することはできない。二人の背後に一貫した思考や共感がなければ、ゲンゴにはならないのだ。かくしてクローン生成されたペアである「大使」が生み出され、ホストたちとコンタクトを取るようになった。また、ゲンゴには仮定や比喩が存在せず、事実しか述べることはできない。従って、比喩を述べたい場合、その比喩を表す人間を設定し、その人間(「直喩」と呼ばれる)を目の前にして語ることになる。要するに、「彼女の瞳はまるでダイヤのようだ」と言いたいときには、目の前に「ダイヤの瞳を持つ女」を表す「直喩」がいないとダメなわけだ。
この突拍子もないゲンゴの設定だけで、もうぞくぞくするよね。『バベル-17』にしろ『神狩り』にしろ、人間とは異なる超越的概念を描く際に言語からアプローチする手法というのは、そもそもサピア=ウォーフの仮設(言語こそが話者の世界観を形成し概念を作るものである)を基にしている。この仮説を逆手に取れば、たとえ理解できないと思われる存在であっても、言語の規則が理解できれば彼らの考えていることがわかるということになる。これがサイエンス・フィクションの方法と親和性が高いことは言うまでもない。有効性がかなり薄れた現在においてもなお、この仮説の魅力は薄れていないようで、本書は、その良い実践例となっている。
さて、主人公はエンバシータウンで生まれ育ったアヴィスという女性。彼女は、あちこちの都市を渡り歩きながら通常宇宙(マンヒマル)の背後に存在する恒常宇宙(イマー)に潜るイマーサーという仕事に就いていたが、ペルシアスという都市で異星言語学者サイルと出会ったことがきっかけとなり、故郷エンバシータウンに帰ることになる。そこで体験した様々な事件が、自身の生い立ちを交えて、彼女の口から落ち着いた口調で語られていく。クローン生成ではない赤の他人二人による大使エズ/ラーの赴任が引き起こしたアリエカ人への意外な反応、さらにはそれが惑星を揺るがす一大事件に発展していくとは誰も気づかなかった……。
落ち着いた語り口とは裏腹に次々と衝撃的な展開が待ち受けており、決して読者を飽きさせることはない。解決にやや安易さが見えることと、「直喩」の描き方が、ネイティヴ・アメリカンの名付け方の域を出ていないことなど不満はいくつかあるが、それでもこれだけ楽しませてくれたのだから文句はない。かつて『闇の左手』において文化人類学的手法をSFに融合させたル・グウィン本人が本書を絶賛しているのも当然だろう。もう一冊『クラーケン』が今年中に出るとのことで、チャイナ・ミエヴィルの快進撃はまだまだ続きそうだ。
西崎 憲『世界の果ての庭』 ― 2013-05-21 17:05

いつものように文庫データベースの更新をしていて、本書のデータを打ち込んでいたところ、はたと困った。いつも本の形式を「長編」「短編集」「アンソロジー」に分類して備考欄に記入している。本書は「長編」のつもりでそう記入しようとしたら、サブタイトルに「ショート・ストーリーズ」とある。え? これ短編集なの。日本ファンタジーノベル大賞受賞作だし、章番号も振ってあるので、てっきり長編だと思ってたんだけど。念のためにと思って読み始めたら、面白くて面白くて、一気に読み切ってしまった。
結論から言うと、これはれっきとした「長編」である。関連したいくつかのエピソードが交互に語られるという構成をとっているので、そのエピソードを一つ一つ切り出して元の形に直せば、なるほど「短編集」にはなるだろう。しかし、それでは本書の面白さはほぼゼロにうななってしまう。英国へ留学して庭の研究をした女流作家の話、江戸時代に一種の言語哲学を独自に編み出し和歌のフレームまで作成した学者の話、ビルマで軍から脱走し無数の階段から成る異世界に入り込んだ男の話、日々若くなる母の話、一見何の関連もない話同士が結びつき、ほぐれ、また結びついていくところに本書の面白さがあるのであって、とにかく作者の手のひらで転がされることに快感を覚える類いの小説なのである。英文学と江戸文学を自在に行き来する闊達さには、さすがアンソロジスト、翻訳家として名を知られるだけのことはあると思わずうならされてしまった。無数の階段がある世界は恐ろしいと同時に実に魅惑的で、トマス・パーマー『世界の終わりのサイエンス』に登場する部屋を連想した。途中で提出された謎も一つは見事に解き明かされ、そこだけは暗号解読ミステリとして十分楽しめるが、もちろん、すべての事件に解決が与えられるわけではない。それなのに/だからこそ本書は面白い。他にもあれば、もっと作者の小説を読んでみたいと思った。
結論から言うと、これはれっきとした「長編」である。関連したいくつかのエピソードが交互に語られるという構成をとっているので、そのエピソードを一つ一つ切り出して元の形に直せば、なるほど「短編集」にはなるだろう。しかし、それでは本書の面白さはほぼゼロにうななってしまう。英国へ留学して庭の研究をした女流作家の話、江戸時代に一種の言語哲学を独自に編み出し和歌のフレームまで作成した学者の話、ビルマで軍から脱走し無数の階段から成る異世界に入り込んだ男の話、日々若くなる母の話、一見何の関連もない話同士が結びつき、ほぐれ、また結びついていくところに本書の面白さがあるのであって、とにかく作者の手のひらで転がされることに快感を覚える類いの小説なのである。英文学と江戸文学を自在に行き来する闊達さには、さすがアンソロジスト、翻訳家として名を知られるだけのことはあると思わずうならされてしまった。無数の階段がある世界は恐ろしいと同時に実に魅惑的で、トマス・パーマー『世界の終わりのサイエンス』に登場する部屋を連想した。途中で提出された謎も一つは見事に解き明かされ、そこだけは暗号解読ミステリとして十分楽しめるが、もちろん、すべての事件に解決が与えられるわけではない。それなのに/だからこそ本書は面白い。他にもあれば、もっと作者の小説を読んでみたいと思った。
宮内悠介「盤上の夜」 ― 2013-05-22 16:05

ずっと気になってはいたのだが、今まで読まずに来てしまった宮内悠介の「盤上の夜」を読んでみた。創元SF短編受賞作は一応すべて読んでいる。松崎有理「あがり」はリーダビリティの高さと奇想がうまく融合されていて素直に楽しめたし、酉島伝法「皆勤の徒」の作風は好みではないけれど、その異様な迫力には圧倒された。理山貞二「すべての夢|果てる地で」は先人へのオマージュに好感が持てる力作であった。どれも日本SFの先行きに期待が持てる佳作であることは間違いない。
『世界の果ての庭』が面白かったので、何の関係もないが(創元から出ている新人というだけだ)、勢いで『原色の想像力』を手に取り、「盤上の夜」を一気に読む。これは傑作。SF短編賞の第1回を選ぶとなると、科学性の希薄さ故にためらうかもしれないが、ジャンルを抜きにすれば、紛れもない傑作である。直木賞候補になったのも頷ける。四肢を失った少女が囲碁を通じて観念の世界を彷徨う。サピア=ウォーフ仮説も登場するので、ミエヴィル『言語都市』との比較も可能である。ミエヴィルが異星人を用いて言語と思考の関係を考察したのに対して、宮内悠介は四肢のない少女を用いて同じ問題を考察したのだ、と。本作はれっきとした言語SFであり、しかも優れたサイエンス・フィクションであると私は思う。短編集全体を読まずに一作だけでレビューするのもどうかとは思ったが、とりあえず記しておきたいと思った次第。
既に本作の面白さをご存知の方には何を今さらの話であるが、未読の方はぜひ読んでほしい。これで受賞できないのだから、創元SF短編賞恐るべし、である。それだけ若く豊かな才能がここから出てきているということなのだろう。徳間の新人賞がなくなってどうなるかと思われたが、これなら安心(むしろ、徳間からはいったい誰が残っているのか? これについては、自分が一次選考をしていた経緯も含めて、また別の機会に触れたい)。第4回の受賞作も最近発表されたので、今から読むのが楽しみである。
『世界の果ての庭』が面白かったので、何の関係もないが(創元から出ている新人というだけだ)、勢いで『原色の想像力』を手に取り、「盤上の夜」を一気に読む。これは傑作。SF短編賞の第1回を選ぶとなると、科学性の希薄さ故にためらうかもしれないが、ジャンルを抜きにすれば、紛れもない傑作である。直木賞候補になったのも頷ける。四肢を失った少女が囲碁を通じて観念の世界を彷徨う。サピア=ウォーフ仮説も登場するので、ミエヴィル『言語都市』との比較も可能である。ミエヴィルが異星人を用いて言語と思考の関係を考察したのに対して、宮内悠介は四肢のない少女を用いて同じ問題を考察したのだ、と。本作はれっきとした言語SFであり、しかも優れたサイエンス・フィクションであると私は思う。短編集全体を読まずに一作だけでレビューするのもどうかとは思ったが、とりあえず記しておきたいと思った次第。
既に本作の面白さをご存知の方には何を今さらの話であるが、未読の方はぜひ読んでほしい。これで受賞できないのだから、創元SF短編賞恐るべし、である。それだけ若く豊かな才能がここから出てきているということなのだろう。徳間の新人賞がなくなってどうなるかと思われたが、これなら安心(むしろ、徳間からはいったい誰が残っているのか? これについては、自分が一次選考をしていた経緯も含めて、また別の機会に触れたい)。第4回の受賞作も最近発表されたので、今から読むのが楽しみである。
ロッド・スチュワート&フェイセズ「ライヴ」 ― 2013-05-23 21:18
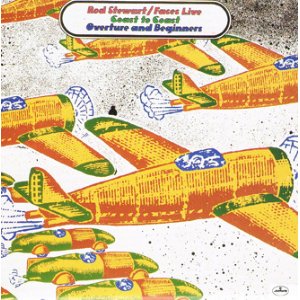
たまには音楽の話も書こう。昔からロッドの初期アルバムは大好きでよく聴いていた。曲で言えば、「マギー・メイ」「ユー・ウェア・イット・ウェル」あたり。アルバムで言えば「ガソリン・アレイ」よりも「ネヴァー・ア・ダル・モーメント」が本当に好きで何度聴いたかわからない。その後、プログレに凝ったこともあるし、アメリカに渡ってからのロッドの曲にはあまり魅かれなかったこともあって、CDはすべて売ってしまった。その中にロッド・スチュワート&フェイセズの「ライヴ」(1973年)もあったはずだ。山川健一が何かの雑誌で褒めていたのが気になって、輸入CDを買ってきたのだと思う(当時はこまめにCD屋を回っていた)。今に至るまで日本版は出ておらず、アマゾンでは、このCD、とんでもない値がついている。
バンド・メンバーはロン・ウッド(g)、ケニー・ジョーンズ(dr)、イアン・マクレガン(key)、山内テツ(b)。つまりはフェイセズからロニー・レイン(b)が抜けて山内テツが加入した直後のライヴというわけだ。バンドの息はぴったり合っており、ラフな感じでありながら、きっちりと聴かせどころは押さえており、このバンドの良さが最大限発揮されている。メンバーのソロも生き生きとしており、会場と一体となって皆が楽しんでいるのがよくわかる。ロッドのソロアルバムからの曲も多く、「マギー・メイ」こそ入っていないが、ロッドの初期ベストアルバムとしても十分通用する選曲だ。「ジェラス・ガイ」のカバーはアルバムでも聴けるが、こちらの方がこなれた演奏で絶対にアルバムよりも出来がいい。全体を通して、ギター・ソロもいいけれど、マクレガンのピアノがバンドのキーを決めている印象を受けた。シンプルであるが故に何度聴いても飽きが来ない(いや、売ってしまったということは当時は飽きていたんだろうが)。20代ではこのアルバムの真の良さがわからなかったんだろうなあ。ああ、売るんじゃなかった。知り合いのカセットテープをA/DコンバーターでPCに取り込み、CDに焼いて聴きながら、若さゆえの過ちを悔いる今日この頃であった。
バンド・メンバーはロン・ウッド(g)、ケニー・ジョーンズ(dr)、イアン・マクレガン(key)、山内テツ(b)。つまりはフェイセズからロニー・レイン(b)が抜けて山内テツが加入した直後のライヴというわけだ。バンドの息はぴったり合っており、ラフな感じでありながら、きっちりと聴かせどころは押さえており、このバンドの良さが最大限発揮されている。メンバーのソロも生き生きとしており、会場と一体となって皆が楽しんでいるのがよくわかる。ロッドのソロアルバムからの曲も多く、「マギー・メイ」こそ入っていないが、ロッドの初期ベストアルバムとしても十分通用する選曲だ。「ジェラス・ガイ」のカバーはアルバムでも聴けるが、こちらの方がこなれた演奏で絶対にアルバムよりも出来がいい。全体を通して、ギター・ソロもいいけれど、マクレガンのピアノがバンドのキーを決めている印象を受けた。シンプルであるが故に何度聴いても飽きが来ない(いや、売ってしまったということは当時は飽きていたんだろうが)。20代ではこのアルバムの真の良さがわからなかったんだろうなあ。ああ、売るんじゃなかった。知り合いのカセットテープをA/DコンバーターでPCに取り込み、CDに焼いて聴きながら、若さゆえの過ちを悔いる今日この頃であった。
諫早創『進撃の巨人』 ― 2013-05-25 02:52
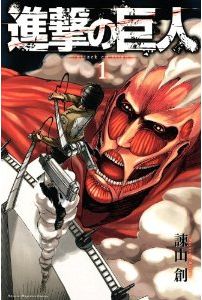
中間考査も終わり、生徒も重圧から解き放たれて伸び伸びと活動している。今日は校内で二本の棒を手にして振り回しながらジャンプしている女子高生を見かけたが、「イェーガー」などと叫んでいたので、あれはおそらく『進撃の巨人』ごっこをして遊んでいたのであろう(どんな学校だと思われるかもしれないが、いわゆる普通の進学校である)。
このように、一部生徒の間で人気の高い『巨人』であるが、決して軽い作品ではなく、読後感はかなり重い。陰鬱で残酷な描写も多数あり、万人向けの漫画とは言い難い。アニメーションになると聞いたときは、え? ホントにやるのといった驚きがあった。きちんと全部観ているわけではないが、数話観た限りでは、原作に忠実に作られており、作画、背景も丁寧でクォリティは高い。この出来栄えなら原作のファンも納得するだろう。
正体不明の巨人から逃れて、壁の中に閉じこもって暮らす人間たちの前に再び巨人が襲いかかる。巨人たちの目的はただ一つ、人間をむさぼり食うことだ。巨人を倒すにはうなじの肉を素早く的確にそぎ落とすしかない。ガスを燃料とした立体起動装置を駆使して巨人に立ち向かう調査兵団の若き兵士たちが本書の主役である。訓練および実戦を通じて苦難を乗り越えていく彼らの姿が描かれるという大筋だけ見ると普通の少年マンガなのだが、その苦難が並大抵のものではない。グロテスクな巨人に仲間が次々と食われていくという凄惨な場面には、思わず目を背けたくなる。非力な自分だけでは過酷な運命には逆らえない、どうにもならないという閉塞感、無力感は、グローバル社会の中で強烈な競争にさらされている若者にとってリアルな実感なのだろう。巨人とは、現実社会の隠喩でもあると分析するのはたやすいことだ。
しかし、作者は「人類対巨人=若者対現実社会」という単純な図式を周到にずらしていく。主人公エレン・イェーガーは医師である父に何らかの処置を施された結果、自らの意志で巨人になれる能力を獲得しており、巨人と人間を繋ぐ存在となっている。ただし、巨人になったときには自らの意志を制御できず味方を攻撃したりするので、意識や知性は抑圧されている。巨人化したエレンは無意識的な破壊衝動、野獣的な生存本能を体現した存在なのだ。過酷な現実社会、すなわち自らの外部を象徴していたはずの巨人と、自らの内部を象徴する巨人とが戦ううちに、両者が入り混じり、違いが徐々に無化されていく。ネタばれになってしまうので詳しくは書けないが、敵だと思っていたらそれが仲間だったり、仲間が敵になったりという十巻までの展開は、「人類対巨人」の図式を「人類=巨人」へと移行していくかなりスリリングな試みとなっている。特に十巻のラストには、おいおい、いくらなんでもそれはないだろうと驚愕させられた。この先がどう展開していくのか、ちょっと目が離せない作品である。
このように、一部生徒の間で人気の高い『巨人』であるが、決して軽い作品ではなく、読後感はかなり重い。陰鬱で残酷な描写も多数あり、万人向けの漫画とは言い難い。アニメーションになると聞いたときは、え? ホントにやるのといった驚きがあった。きちんと全部観ているわけではないが、数話観た限りでは、原作に忠実に作られており、作画、背景も丁寧でクォリティは高い。この出来栄えなら原作のファンも納得するだろう。
正体不明の巨人から逃れて、壁の中に閉じこもって暮らす人間たちの前に再び巨人が襲いかかる。巨人たちの目的はただ一つ、人間をむさぼり食うことだ。巨人を倒すにはうなじの肉を素早く的確にそぎ落とすしかない。ガスを燃料とした立体起動装置を駆使して巨人に立ち向かう調査兵団の若き兵士たちが本書の主役である。訓練および実戦を通じて苦難を乗り越えていく彼らの姿が描かれるという大筋だけ見ると普通の少年マンガなのだが、その苦難が並大抵のものではない。グロテスクな巨人に仲間が次々と食われていくという凄惨な場面には、思わず目を背けたくなる。非力な自分だけでは過酷な運命には逆らえない、どうにもならないという閉塞感、無力感は、グローバル社会の中で強烈な競争にさらされている若者にとってリアルな実感なのだろう。巨人とは、現実社会の隠喩でもあると分析するのはたやすいことだ。
しかし、作者は「人類対巨人=若者対現実社会」という単純な図式を周到にずらしていく。主人公エレン・イェーガーは医師である父に何らかの処置を施された結果、自らの意志で巨人になれる能力を獲得しており、巨人と人間を繋ぐ存在となっている。ただし、巨人になったときには自らの意志を制御できず味方を攻撃したりするので、意識や知性は抑圧されている。巨人化したエレンは無意識的な破壊衝動、野獣的な生存本能を体現した存在なのだ。過酷な現実社会、すなわち自らの外部を象徴していたはずの巨人と、自らの内部を象徴する巨人とが戦ううちに、両者が入り混じり、違いが徐々に無化されていく。ネタばれになってしまうので詳しくは書けないが、敵だと思っていたらそれが仲間だったり、仲間が敵になったりという十巻までの展開は、「人類対巨人」の図式を「人類=巨人」へと移行していくかなりスリリングな試みとなっている。特に十巻のラストには、おいおい、いくらなんでもそれはないだろうと驚愕させられた。この先がどう展開していくのか、ちょっと目が離せない作品である。
最近のコメント